
子宝ロダンは、ブロガーである。
他人のセックスを克明に報告するブログをあげている。
まわりが、ことごとく妊娠する、ゆえに「子宝」と名乗る。
いつか「子宝教」を興すつもり、らしい。
「ロダン」は、オーギュスト・ロダンに憧れて。
「彫刻をひたすらに創り続けて生きる——なんとうらやましい人生であることか」
プロフィールを読むかぎり、まったくいい加減で、ペテン師のような男である。
第1話 黄色玉(前編)
〈1〉
となりに寝ている美由紀がふいに小さくうめき声をあげた。
圭介は背中でそれを聞いた。自分がぐっすりと眠っていたことに改めて気づくような、そんな目覚めかただった。美由紀の声に少しばかり異様な気配を感じて、からだのどこかが反応したのかもしれない。
「どうした」
大きくからだをひねって振り向くと、上半身を起こした美由紀が、ひどく困ったような顔でこちらを見ていた。
「ん」
美由紀は、戸惑いの視線のまま、ゆるく眉をしかめた。くちもとがゆっくりとゆるんで、歯の先が見えた。
「あ……」
声をあげて、両手で腹のあたりをおさえている。へそのあたりに置いた手を揉むようにさげて、顔をしかめながら、ふたたび伸ばす。
下腹のあたりまでかけた布団のなかで、彼女の手がもぞもぞと動いている。
美由紀は、妊娠三か月なのだ。
その腹部に重大なことが起こっているのかもしれないと圭介はおびえた。なにをどうすればいいのか、まったくわからなくて、手をさしのべることもできない。
胸のあたりが縮みきって、苦しかった。
あえぐように息を吐いて、
「どうしたんだ」
と、ようやく、かすれた声で言うことができた。
「ちょっと待って」
つぶやいたあと、美由紀はしばらく黙ってから、右手を布団から抜いた。
「これ……」
見る前からわかっているような顔つきだった。
彼女の親指とひとさし指のあいだに、一センチほどの大きさのガラスの玉があった。黄色いビー玉だ。指先で触れたとたん、彼女にはそれがビー玉だとわかったようだ。
みょうな感じで美由紀の眉が上下になっている。複雑な表情だ。
「なんで?」
と、圭介は声をあげた。気のせいか、ビー玉は温かくぬめりを帯びているように見えた。
圭介は自分が目を見開いてしまっていることに気づいた。
「これって……」
「いま」
美由紀は首をかしげながら続ける。
「出てきた……」
「どこから」
「下着のなか……」
「そんなこと……」
あるはずがないのだった。もう夜中の一時をまわっている。たとえそれが朝の七時だろうが午後三時だろうが同じことだ。ビー玉が下着のなかから出てくるのは、いつだろうと奇妙だ。
「おなかのなかから出てきたような……」
と、首をかしげ、
「気のせいだと思うんだけど」
美由紀は、言葉を切った。
圭介がゆるゆると差しだした左手のうえに、美由紀がビー玉を置いた。
圭介には、美由紀があまり驚いていないことが不思議だった。きっとほんとうはベッドのうえに落ちていたのだとでも考えているのだろうか。そうかもしれない。シーツのうえを転がっていたのかもしれないし、下着のなかにまぎれこんでいたのかもしれない。いろいろと可能性はある。
ビー玉を指先でつまんでから、圭介は惚けたように美由紀を見た。
「おなかのなか?」
胃とか腸という意味ではないことは、すぐに理解できた。おなかというのは膣ということだ。
「そんなこと……」
ふたたび圭介はつぶやいた。それは、ありえない。
「気のせいだと思うんだけどね」
美由紀の表情は明るいものをふくんでいる。
「でも……そんな気がするのよ」
「痛いとか、そういうのは?」
「大丈夫……」
美由紀はやわらかく笑って、そして続けた。
「どっちかって言うと……」
ほんのりと、目もとが赤らんだような気がした。そのせいなのかどうなのか、彼女はそこで言葉を飲みこんだ。
その顔つきは圭介に不思議な感覚を呼び起こさせた。まったく不意の、唐突な思いつきだった。
やわらかく、美由紀の肩を抱き寄せた。美由紀もそのことをこばまない。
圭介は腰にまわした右手を撫でるようにまさぐった。まさぐりながらパジャマをめくり、うしろから下着のなかに手を差し入れた。伸ばした指がくねくねといきつくと、そこは、すでにたっぷりと湿り気を帯びて熱かった。
「だめ」
美由紀は両手で圭介の肩をつかんで、首をふった。瞳は、はっきりとうるんでいた。けれど、もう一度、顔をしかめた。
「だめだめ」
もしかすると、と、圭介はふいに思った。きょうの夕方、美由紀は定期検診で前川産婦人科に行ったはずだ。そのときに、前川医師が彼女のなかにビー玉を入れたのではないか……と、なぜか、そんなことを想像した。
産婦人科医が検診中に腹部に異物を挿入することが許されるのかどうかわからない。が、そういうことができる機会が、前川医師にはあったし、彼しかそんなことはできないのだ。
前川医師の指がゆっくりと美由紀のなかにビー玉を入れる……圭介は、その瞬間を想像して少しばかり興奮していた。ひどくセクシーな想像だった。なにより、実際に、美由紀が性的に興奮している。それは心地よい感触だ。
「んん……」
美由紀があえぐ。圭介の指先もぬかるみのなかにゆっくりと侵入する。
前川医師のしわざであるにしろないにしろ、ビー玉が現れたことで、圭介はこれまで経験したことのない不思議な気持ちになった。
美由紀が、ぼんやりと眼をあけた。照れたように笑った。こんなにおだやかな顔を見るのは、ずいぶんひさしぶりだと圭介は思った。

ビー玉は、圭介が一週間ほど前に手に入れたものだ。
子宝ロダンというブロガーから買った。
百円だった。
どこといって珍しいものではない。ごくふつうのビー玉だ。きっと百円ショップにでも行けば一握り程度を百円で買えるだろう。
「手放しの玉」
と、子宝ロダンは呼んだ。
「ずっと持ってちゃだめなんです。手放さないと、だめ」
決めつけるようにロダンが言うものだから、圭介はつい、
「だめって、なにがです?」
と、訊いた。
すると、ロダンは、ごくふつうの顔つきで、
「おもしろくないんですよ」
などと言う。
「おもしろくない?」
「そう、おもしろくない。せっかく百円も出して買うんだから、おもしろくないとね」
「ははぁ。すると、百円で買って手放せば、おもしろいことが起こる?」
「はい。期待していいです」
そこまで言われて財布から百円硬貨を出さない者は、たぶんいない。
そのときのことを思い出しながら、圭介は、ベッドの背もたれにクッションを押しつけ、つまんだビー玉を見つめた。
となりで美由紀は寝息をたてている。
ひさしぶりに愛情に溺れるようにして、美由紀を抱いた。妊娠していることを気にしてあっさりとしたつもりだが、気持ちのいいセックスだった。その気持ちよさとこのビー玉が関係しているような感じがするし、その感じを追いかけるとどこか違うところにいけそうな気もした。
ベッドサイドに置いてあるスタンドの豆電球が、黄色いガラス玉に、澄んだ光の輪郭を与えている。圭介の指先が輝いて見えた。
美由紀は、それがおなかのなかから出てきたと言う。そんなことが、あるのだろうか。
(手放しの玉……)
美由紀の背中は、寝息にあわせてゆっくりとゆれている。
あんなところからこんなものが出てきたというのに、本人は平気のようだ。
もしかすると、美由紀のいたずら、なのだろうか。ビー玉を買った話は、子宝ロダンと会った日に笑い話のようにした。だからきっと、それを覚えていて、美由紀が自分をからかったのだと考えてみると、とても常識的で納得できる。
「手放しの玉、すかさず手放すべし」
買ったときに子宝ロダンはちょっとした説明をした。できるだけ速やかに自分の手から放すべし。家のなかのゴミ箱とか庭に埋めるなどはいけない。それでは手放したことにならない。
「いちばんのおすすめは、コンビニの入り口のところにあるゴミ箱ですね。ガラス瓶なんかも仕分けされてるでしょ。あのガラス類のところに入れるといいですね。ビルの屋上から道路に向かって捨てる、なんていうのはだめです。投げるべからずです。危ないですから」
子宝ロダンの家から近い石川台駅の近くに神社がある。帰るときにその神社に立ち寄り、賽銭箱に十円玉といっしょにビー玉を放りこんだ。カチャンカチャンと大きな賽銭箱の底のほうで音がしたのも聞いた。
いま指先でつまんでいるのと同じ黄色いビー玉だ。ガラス全体がくっきりとした黄色。
世田谷通り沿いの圭介のマンションから東急池上線沿線の子宝ロダンの家まで電車で一時間ほどかかる。世田谷線で三軒茶屋まで行き、田園都市線に乗り換えて渋谷まで。渋谷から山手線、五反田駅から池上線だ。地図上ではほぼ南に一直線だが、電車だとぐるりとまわらないといけない。ビー玉が転がる距離ではない。
豆電球の弱い光は、ビー玉のなかで妖しげな輝きを増しているような気がする。
手放しの玉——。
美由紀のおなかからこんなものが出てくるのが、おもしろいかどうかはわからない。
ただ、さっき美由紀からビー玉を渡された瞬間、うまく言えないが、なにかが変化したような気はした。どこがどう、とは、定かではない。車で走っていてトンネルを抜けるとふいに天候が変わっていた、みたいな。部屋のなかの照明の色合いが変化したような。
もしかすると、美由紀の静かな寝息が、そう思わせるのかもしれない。なぜだか、圭介はそんなふうに考えた。
彼女のこんなにおだやかな気配はひさしぶりだった。
きっと、いちばんの変化はそこだということに気づいて、圭介も静かな眠りにひきこまれそうになった。握りしめた手のなかで、ガラス玉は生きているような熱を帯びていた。
〈2〉
二日後。
圭介は、池上線の石川台駅で電車をおりた。改札口を出て右に行くと八幡神社がある。先週、賽銭箱にビー玉を放りこんだ神社だ。
寄っていこうとも思ったが、約束の時間が迫っているので、あとにすることにした。
九月だというのに、ずいぶんと涼しい日が続いている。
駅から子宝ロダンの自宅まで、少し距離がある。なによりも神社の前の坂がかなり急だ。涼しいのはありがたかった。
圭介は、神社の角を左に折れ、宮前坂という名の急坂をゆっくりとのぼった。
午前中に電話すると、子宝ロダンはいつでも大丈夫ですよと言ってくれた。先週もそんなふうに当日のアポイントメントで時間が取れた。
ヒマなのかもしれない、と、圭介は思う。
子宝ロダン、という男がどうやって生きているのか、詳しいことはなにも知らない。圭介が知っているのは、子宝ロダンという名前でブログを書いているということだけだ。
サイトのおもなテーマは、夫婦やカップルのセックスだ。
圭介も男なので、ときどき、というか頻繁に、というかたぶん世間並みの頻度で猥褻なページを眺める。そんなときに偶然見つけたのが子宝ロダンのブログだった。
子宝ロダンは、どこかでおこなわれるセックスをじっさいに目の前で見て、それをレポートしていることが多い。馬鹿馬鹿しいほど真っ正直に、自分が見てきたカップルや集団の性態を記録している。ブログのなかで子宝ロダンは、わりと無愛想で男っぽくて猥雑だ。それでもぎりぎりのところで品が保てているところに好感が持てた。
彼のブログの熱心なファンがいて、子宝ロダンを自分のところに招待するようなのだ。そうやって子宝ロダンはいろいろな場所を訪問している。愛好家のパーティやら撮影会などにも呼ばれるようだ。
スワッピングやカップル喫茶のような場面も毎回のように登場する。
子宝ロダンはアダルトビデオのスタッフにも知り合いが多いらしく、男優を素人カップルたちのところに派遣したりもしている。
ホテルのスイートルームのような場所に滞在する外国人の男を訪問、なんていうのもある。金髪で大柄な外国人はコスプレ願望があるらしく、子宝ロダンは大きなサイズのセーラー服を用意して、その男に着せてやる。セーラー服を着てうれしそうにポーズを取る白人の男の写真が、子宝ロダンの文章とともに掲載されている。
ブログではメールも受けつけていて、セックスや夫婦関係の悩み相談のようなこともやっている。不妊の話題もけっこう多い。
そもそも、なぜ「子宝ロダン」なんていう名前かというと「まわりのひとが、ことごとく妊娠する」からだそうだ。つまり、彼といると子宝に恵まれる、らしい。
「いつかは子宝教をおこして教祖になろうと思い」
などという一文がプロフィールにある。
ロダンについては「彫刻家、オーギュスト・ロダンに憧れて」とある。
「彫刻をひたすらに創り続けて生きる——なんとうらやましい人生であることか」
プロフィールを読む限り、まったくいい加減で、ペテン師のような男だ。
実は、圭介は、そのペテン師のような子宝ロダンのブログに相談メールを書いたのである。
それほど、追いつめられていたと言えるかもしれない。
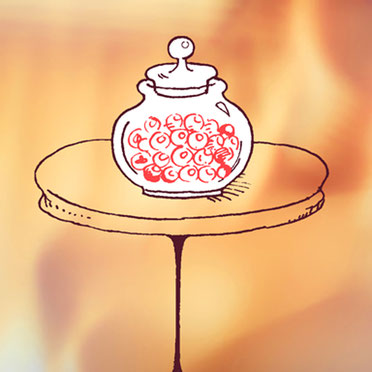
実は、圭介と美由紀は不倫関係にある。
圭介はいま三十六歳の独身だが、美由紀には夫がいる。美由紀は三十三歳だ。
出逢いは……インターネットの掲示板だった。
彼女の夫が「妻を誘惑してくれませんか」と依頼していた。
結局のところ、圭介も、いかがわしい場所で女との出逢いを求めたことになる。子宝ロダンのブログみたいな展開だと、ほんとにその時期、思っていた。ただ、いろいろエロいサイトを覗きはするが、それまでインターネットの掲示板に一度も興味を持ったことはなかった。
けれど、そのときは、なぜか「ぐっ」ときた。
「妻はリス顔です」
そのひとことにやられたのかもしれない。
リス顔の女が、圭介は昔から好きなのである。
掲示板の投稿を熱心に読んだ。その人妻を誘惑して肉体関係に持ちこむことに、はじめから自信があったわけでもない。が、依頼内容に描かれている「妻の雰囲気」に、脳のどこかがしびれていた。
掲示板に書きこんでいた男は「中野」と名乗っていた。年齢は三十代前半のようだ。メールのやりとりから伝わってくる印象は「まじめ」で「そつがない」。
そういう男がはじめて掲示板に書きこんだ……というのだが、その部分はどうにも信用はできなかった。言葉づかいなどが、掲示板とかメールでのやりとりにとても慣れているような気がした。ふだんからそういう仕事をしているような気配があった。
けれど、妻に関しての依頼ははじめて——そこは間違いないと思えた。
「ごくふつうのおとなしい女です。私以外にはほとんど男を知らないと思います」
そういうふうに説明する中野という男の語りくちも、誠実な雰囲気があって悪い感じではなかった。
妻を愛しているからこそ望む……という彼の気持ちを知るほどに、そんな彼の妻なのだからきっと誠実で美しいに違いないと思えた。
車の中古部品を掲示板を利用して買ったことが二度ほどあるだけの圭介なので、人妻を誘惑する計画を夫と練るなど、ひどく緊張して、なにをどう考えていいのかさえわからなかった。それでもきっと相手のリードがうまかったのだろう、話はどんどん具体的に進んでいった。
一か月ほど、中野とメールのやりとりを続けた。途中何枚か自分の写真を送った。相手の妻の写真も見た。想像よりすっきりして見えた。かわいいリスを思わせた。まったく悪くない。どこにでもいるおとなしそうな女性だった。三十三歳にしては落ち着いた雰囲気だと圭介は思った。
中野からのメールで指示を受け二度ほど買い物をする姿を遠目に見た。最初に美由紀に声をかけたのが、昨年の十二月なかば。そこからクリスマス、正月を経て、最初は偶然を装い、お茶に誘い食事に誘い……と、ずいぶん時間をかけて「誘惑」に向けた準備を重ねた。
強引にセックスに持ちこまなかったのは、美由紀がごくふつうにまじめな性格だったこともあるし、圭介にとって会話だけで充分に楽しい女だったからだ。
会話の内容や美由紀の態度については、毎回細かく中野にメールで報告した。中野も詳細に返事をくれるし、次回はこういう話題がいいかもしれないと提案してくる。
夫からもたされる情報は、美由紀との会話を盛りあげるうえでとても役立ったのは確かだが、しだいに、そんなものに頼らなくても、美由紀との仲が親密になっていることを実感できた。
ふたりは、夫の密かな応援を背景にして、しだいに精神的にも結びついていった。その実感が圭介には心地よかった。
そして、今年の三月。いよいよ、最後の一線を越えるときがきた。
それまで、夫である中野が美由紀とどういう会話をしてきたのか、圭介は知らない。ふたりの夫婦生活についてはほとんど教えられていないのだ。中野も言わないし、美由紀も語りたがらない。とても良好というわけではないが、決定的に冷めているわけでもない。そんな感じだった。ただ、子どもを欲しがっているというような話題になったことはある。
三月十三日。金曜日。
その一週間前に指をからめるように約束して、美由紀は充分に覚悟していたと思う。
中野が週末、出張に出かける日に、美由紀も高校時代の女ともだちと箱根に一泊旅行をする。そんな計画だった。
ところが、待ち合わせの場所に美由紀が現れなかった。それどころか連絡も取れなくなった。携帯もつながらなくなりメールにも返事がない。
中野にメールを入れて事態は判明した。彼が土壇場になってストップしたのだ。美由紀にすべての事情を話し、
「行かないでくれ」
と、涙を流したらしい。
ひどい話だ。と、圭介は鉛を飲んだような気持ちになった。馬鹿野郎、と、中野を大声で殴りつける自分を想像した。とにかく美由紀にとって残酷すぎる、と、気づいたとたん、圭介は駆け出していた。自分も夫と同類で、憎まれるべき存在だと自覚したうえで、なお、彼女を救い出すべきだった。
強く、そう思った。
すべて、ゲーム。なにからなにまで計画どおり。目的はただ肉体的に誘惑することだけ——。
いまごろ彼女は暗闇の底に放りこまれているだろう。
助けなければいけない。そう自分に言い聞かせることが、全身に広がる衝撃的な敗北感に、唯一打ち勝つ方法だったのかもしれない。
美由紀の住むマンションは参宮橋にある。何度か送ったことがあるのでよく知っていた。夫がいるのだから部屋にはあがったことはないけれど、その日は乗りこむつもりだった。
箱根に行くための待ち合わせ場所は新宿駅の近くだったので、参宮橋までなら十分たらずだ。その途中にも美由紀にメールを入れた。
(来ないで、会いたくない。もう会わない)
それまで無反応だったのだが、さすがに家に行くと宣言したものだから、そんな返事がきた。
(だめだ。旦那をぶん殴ってでも、きみを奪いにいく)
そう書いて、それから何度も「愛してる」と書き連ねた。
極度の興奮状態だったと思う。夫によって完全に関係を断たれたからこそ、美由紀への思いが爆発した。
それは、美由紀も同じだったのかもしれない。
爆発したのだ。
方向が定まらないまま破裂した感情は、激しい行動を呼び、その行動に突き動かされて、うねった。
マンションの前にある公園の入り口のところに彼女は立っていた。泣いていた。
「もう会いたくない」
美由紀は何度もそう言った。
「行こう」
圭介は彼女の腕を強くひいた。予約したホテルに行こうにも、彼女は手ぶらでサンダル履きだった。いまさら荷物を取りに部屋に戻すわけにもいかない。
「とにかく、行こう」
「だめ」
激しく抵抗する美由紀に、圭介は声を荒げた。
「旦那のところに帰したくないんだ。きみは、あいつと別れるべきだ。おれと結婚しよう」
新宿から参宮橋まで来るあいだに考えていたことだ。こんな状態でプロポーズするのが得策なのかどうか、圭介にはわからなかった。興奮していた。すべての計画を台無しにした夫の裏切りを大逆転してやりたかった。
「頼む、もうぼくにはきみしかない。愛してる、ほんとに」
「それも演技? 彼に頼まれたの?」
美由紀は強烈な皮肉を、涙だらけの声で絞りだした。
「違う」
圭介はちょうど目の前にやってきたタクシーに手をあげて、美由紀の腕をつかむと後部座席に押しこんだ。
世田谷通り沿いのマンションに美由紀を連れてきた。圭介は、その夜、美由紀を抱いた。美由紀も激しく応えた。
新しい関係のはじまりだった。
翌日の朝、美由紀は家に帰っていったが、その日からは頻繁に圭介のマンションに来るようになった。圭介は結婚についてまじめに考えたし、彼女とも何度もそれについて話し合った。
「まずは離婚しないと……」
美由紀は、圭介との結婚の話になると、必ず少しつらそうな顔をした。
「なんだい、離婚するのは、いやなのかい?」
「違う。もうあのひととは無理、やってけないと思う。なんだか生理的に受けつけなくなったから……近づいてくるだけで、ちょっと鳥肌がたつっていうか……」
美由紀はそう言って二の腕をさする。
ただ、そうやって夫のことを嫌悪するようになったにしろ、離婚となるとハードルは高いことを美由紀は知っている。なにより夫は美由紀のことを溺愛しているのだ。だからこそ、あんな計画を立てたし、愛しているがゆえに土壇場で止めた。
三月から夏にかけて、とにかく、圭介と美由紀は軽い熱病のような状態だった。感情の大きな波のなかで身もだえしながら生きた。会うたびに現状を嘆き、未来を語り、愛を誓い合う。
圭介は、母親に美由紀を紹介した。
圭介の実家は、経堂駅前の農大通りのはずれにある洋服店だ。父親は圭介が高校生のときに心臓病で亡くなった。六年ほど前までひとりで切り盛りしていた母親のあとを継いで、圭介は店舗とはべつにネットショップを立ち上げ、わりとうまく展開できている。
三十六歳の息子が不倫関係にある三十三歳の女を連れてきて最初は面食らったが、母親もそのあたりはいまふうに割り切っているのか、それとも美由紀を気に入ったのか、最初から協力的だった。
「まずは弁護士だね。駅前の小笠原先生ならよくしてくれるはずだから、会いにいきな」
すかさず、母の優子が弁護士の手配をした。
出逢いのきっかけは黙ったまま、圭介は小笠原弁護士に相談した。すぐに弁護士は動きはじめた。
「圭介くんのマンションに転がりこんでるのはどうも印象が悪いから、実家の部屋をひとつあけてもらって、そこに住んでいるということにしたほうがいいね」
昼間からビールを飲んでいる老年の小笠原弁護士は、もごもごと滑舌の悪いしゃべりで圭介と美由紀を不安がらせたが、それでも弁護士らしい口調でこう断言した。
「まぁ離婚なんてものは、どちらかが言いはじめたら、あとは成立に向けて条件闘争だから。美由紀さんがあまり多くを望まないのだから、すぐに解決するでしょう」
七月に正式に離婚協議がはじまった。
美由紀の夫の名前は中野ではなく、花崎征雄といった。最初は順調に解決するように見えた。花崎も離婚に関しては仕方ないとあきらめているらしいという情報が小笠原弁護士から伝えられた。そのころにはもう美由紀は参宮橋に帰ることはなくなり、圭介の実家でほとんどの時間を過ごすようになった。店舗と隣接する客間を美由紀の部屋にした。もちろん実家から自転車で五分くらいのところにある圭介のマンションにも来る。
八月の終わりになって、美由紀の妊娠に気づいたのは、母だった。
「ありゃ、つわりだね」
優子はものすごくうれしそうだった。もう結婚なんてできないと思っていた息子が、嫁と孫をいっぺんに連れてきたと涙ぐみさえした。
優子のすすめで前川産婦人科に検診にいき正式に妊娠が判明したのだが、そのことがなぜか美由紀の夫に知られた。
「きっと小笠原先生が言っちゃったのよ、酔っ払って」
と、美由紀は腹を立てた。
「きっと先生、もう美由紀が妊娠までしちゃって、絶対に戻ってはこないってことを旦那に言いたかったんじゃないかなぁ」
圭介は小笠原弁護士の肩を持つつもりではないが、そう慰めてみた。
「離婚後三百日以内に生まれた子は元夫の戸籍に入るんですなぁ。美由紀さんの場合、まだ離婚も成立してないわけですし」
駅前の事務所に行って面会すると、小笠原弁護士は、呑気な口調でそんなことを言うのだった。
しかも、花崎征雄は、美由紀の妊娠を知ったとたん、離婚拒否に転じたらしい。
「ぜったい別れたくない、その子はぼくの子どもだから、ぼくが育てたいって……こう言うんですなぁ。美由紀さんにも母親として子育てに参加して欲しいと、こうですわ」
小さなコップにビールを注ごうとする小笠原をひっぱたくように上半身を乗り出して、美由紀はきりりとした目で、
「先生が、妊娠のこと、言っちゃったんでしょ」
と、なじった。
「ひどいじゃないですか」
「いやぁ私は言ってないよ。向こうが知ってた。ほんとうだよ」
小さく肩を丸める老弁護士は嘘をついているように見えない。しかし、弁護士が告げてないとすればどうやって花崎がそれを知ることができたのか。
「確か検診の日、美由紀は参宮橋に行かなかった?」
「行った、洋服とか、取りに……」
「そのときに旦那がいた、とか」
「いなかったよ。でも、あのとき……」
大きな目をきょろりとさせて、美由紀は圭介を見た。
「あっちの部屋で圭介と電話で話したよね。病院出たあとすぐにメールしたら、しばらくしてかかってきた」
「うん、電話した。あのとき向こうにいたの?」
「いた……クロゼットの前に座って話してた。もしかして……」
美由紀は、首をすくめて大きく上半身をゆすった。
「盗聴かも。どこかにマイクが仕掛けてある、とか」
「盗聴?」
小笠原弁護士が驚いて声をあげた。
「そりゃまた、念がいってますなぁ」
「先生、ぜったいそうですよ。あのひと、部屋に盗聴器、仕掛けてるんです、きっと」
「仕掛けてるっていっても、それ、自分の家ですわなぁ」
「そういうこと、するひとなんです」
「ほうほう、そうかもしれませんなぁ。インターネットとかもお好きみたいで」
と、意味ありげに小笠原はふたりを交互に見る。
「圭介くんと美由紀さんの、そもそもの出会いの話、聞きましたよ。私にはよくわからん世界ですが……先方はなにやら興奮して、すごい勢いで口から泡とばして話してましたが……」
小笠原は、そう言ってからまじめな顔をしてうなずいている。なにを考えているのか、さっぱりわからない弁護士だ。
「私、堕ろす」
小笠原弁護士の事務所の応接セットで、美由紀は奥歯をかむように言った。
「ぜったい堕ろして、ぜったい離婚する」
目をつりあげた美由紀の横顔を、圭介は茫然と眺めているしかなかった。
美由紀の決意とは逆に、圭介の母は、
「堕ろすのはよくない」
と、はっきりしたものだった。
楽しみにしていた孫を取られるような思いもあるのかもしれないが、それよりもう少しべつの信念みたいなところで反対しているふうでもあった。
「せっかく授かったものを堕ろすなんて罰あたりな……」
小笠原弁護士と会った夕方、実家で話を伝えると、優子は椅子から立ちあがるときに、はずみで口にするような調子で言った。
となりで美由紀は無言だった。
圭介はぼんやりとではあるが産んで欲しいと思っていた。具体的になにかがイメージできているわけではないが、家族が増えるということに甘い喜びのようなものが湧いてくる。
それにしても、美由紀の夫の態度は許せなかった。妊娠したことがわかったとたん、離婚はしたくないと言いだす。子どもは自分の籍に入るのだからちゃんと育てたいなんて、そんなものは屁理屈なのだ。とことん美由紀と圭介を困らせようという魂胆に違いない。そう思うと無性に腹が立つし、美由紀が堕ろすと言い出す気持ちもよくわかる。
それから数日して、花崎征雄から圭介の携帯電話にメールがきた。
「妻のおなかにいる赤ん坊について、圭介さんはぜったいに自分の子だと思っていませんか?」
と、メールは、冒頭からいきなり挑戦的だった。
「美由紀が圭介さんのところから帰ってくると、実は、ぼくも妻を抱いていました。美由紀も、すごく積極的でした。圭介さんのおかげで妻は予想以上に淫乱な女になったようです」
陰湿さに吐き気がした。
それと同時に、美由紀と夫の関係が続いていたことが気になった。三月のあの日、強引にマンションに連れ帰って以来、美由紀は「近づいてくるだけで鳥肌が立つ」と言っていたのに、実はふたりは夫婦であり続けていた——そのことにひどく動揺した。
「圭介さん、美由紀と結婚できると本気で思ってるんですか? 私もだましていたけど、あなたの欺瞞はもっとひどいんじゃないですか? そのことを美由紀が気にしていないと、本気で思ってるんですか?」
携帯電話を床に叩きつけたい衝動をおさえるのに苦労した。
花崎のメールは、圭介の触れたくない心情をみごとに突いていた。
夫への憎悪を軸にして離婚を願い、憎しみゆえに堕胎する。けれど、夫への憎悪の先には圭介の姿だって見えているはずだ。圭介は夫とともに美由紀をだましたのだ。自分はほんとに彼女に愛されているのかどうか、自信はない。
もう少し言えば、自分の感情も、自分で定義できないでいる。
ほんとうにこれは愛なのか?
ほんとに美由紀を愛しているのか?
美由紀を誘惑するというゲームに酔っていただけではないのか?
その不安な気持ちをどういうかたちにも解決しないまま、美由紀に、夫からのメールの件を話した。
圭介のマンションの小さなテーブルをはさんで、ふたりで夕食を食べているときだ。
「ひどいだろ?」
と、弱々しく、圭介は言葉を待つように美由紀を見た。
「最悪」
美由紀は、つばを吐くように言った。
「ほんと、最悪」
もう一度吐き捨てると、美由紀はふいに立ち上がり、
「私、実家のほうに行ってる。しばらくこっちには来ない」
と、肩を怒らせて出ていこうとした。
「待てよ。こっちに泊まってけよ。歩くのは、よしたほうがいいよ」
妊娠安定期に入るまであまり歩かないほうがいいと母が言ってたのを思い出したのだ。
「大丈夫、近いし。それに……」
玄関のところでくっきりと振り向いて、美由紀は圭介をにらんだ。
「この子は、堕ろすんだから」
ようやく手に入れたものが、そうやって去っていくような気がした。
その夜、ひとりでパソコンに向かいながら、圭介はなんとなく子宝ロダンのブログページを眺め、相談コーナーにメールを送った。すぐに返事がきた。電話番号が書かれていて「ぜひ電話をください」とあった。
それが先週の月曜日のことだ。
翌日、圭介は子宝ロダンに会いにいき、黄色いビー玉を買った。
子宝ロダンは、ブログの印象とはまったく違い、ごくおとなしい中性的な雰囲気の男だった。年齢をたずねると「万年厄年です」と照れるように言った。厄年というと四十一とか二とか、そんなところだろうが、とてもそんな年齢には見えない。同い年か少し若いくらいではないかと勝手に想像してみた。
最初に訪問したときに、圭介は、自分でも驚くくらいあっさりと美由紀との馴れ初めからこれまでのことを話した。子宝ロダンのブログからすれば、掲示板で夫に妻の誘惑を依頼されたということなど、珍しくもないような気もした。
「寝取られ、ですね」
子宝ロダンは笑いもせずに、やわらかくうなずいた。
「結婚している男性は、ほぼ全員、寝取られ願望があるって言いますからね。奥さんがほかの男とやるのを想像すると異様に興奮します、みんな」
「みんな……ってことはないと思いますけど」
圭介が苦笑すると、子宝ロダンは首をふる。
「ゲイにとって、ノンケは処女といっしょだって言うの、知ってます?」
「…………」
「つまりね、知らないだけ。寝取られ願望がないっていうのは、知らないだけです。想像したことないだけ」
「そうかなぁ」
首をかしげる圭介の前で、子宝ロダンはゆったりと笑った。
「……というふうに、私、あらゆるジャンルで思ってるわけです。エスもエムも、露出も乱交も、セーラー服も……興味がないっていうひとたちは、きちんと想像していないだけです」
「スカトロも?」
「もちろん。藤森さん、ほんとにいい女がウンコしてるの、想像したことないでしょう?」
すずしい顔をしてそんなことを言うのだが、容貌はまるで古い禅寺の僧のようなのだ。とはいえ坊主頭ではない。スキンヘッドという特徴さえ避けるような短い髪。色のない作務衣を着て、贅肉はなく白すぎるほどの肌。中背。印象が薄いというより、消そうとしている感じ。
それが子宝ロダンなのである。
〈3〉
ほぼ十日ぶりに、東雪谷の住宅地を歩きながら、圭介は、ずいぶんと小高い丘のうえを歩いている気がしていた。周囲の風景を見まわすゆとりもなかった前回と比べ、ずいぶんと今日は気持ちが落ち着いているのかもしれない。
家が途切れると、道路は急坂になって視界が広がり、遠くに背の高いビルがよく見える。
やわらかい風が頬を撫でていく。この前も確か、天気がよくて、夏の暑さを忘れさせてくれるような風が吹いていたのはよく覚えている。
正直に言えば、子宝ロダンに会ってなにかが解決すると思っていたわけではなかった。美由紀とのことを相談できる相手がほかにいなかっただけだ。メールのあと、なぜ会ってみる気になったのかも定かではない。なんとなく。電話で話していて、ふと、いまから来ませんかと言われ、その気になった。行って話してみたら少しだけ気持ちが楽になった。言われるままビー玉を買ったら不思議なことが起きた。
そしてまた、圭介はこの道を歩いている。
このあたりは大きな家が多く、敷地が広い。金持ちがたくさん住んでいるのだろうが、どうして、こんなところで子宝ロダンが暮らしているのか、しかも一軒家に、などと、先週とは違ってあれこれと圭介は思いをめぐらせてみた。
子宝ロダンの家はコンクリートの箱をオレンジ色に塗ったような建物だ。
まわりに同じようなデザインだが大きさと色の違うのが三軒ある。子宝ロダンの家がいちばん小さく、いちばん大きいのは奥にある緑色だ。ほかに濃紺と濃い赤がある。色調はどれも深く落ち着いている。建築家が丹精こめて設計したことは明らかで、周囲に溶けこみながら、それでも近代的で重厚な雰囲気を放っている。
四つの建物に囲まれる庭には大きな桜の木がある。高さは六メートルを超えているだろう。幹は太くゆがんで風格をたたえている。
ゆるやかな風に吹かれて黒々と繁った葉がゆったりと揺れているのを、圭介はオレンジ色の家をいったん通り過ぎて、見た。なにかを確認するように桜の木を見上げてから、玄関前に戻ってきた。
ひとさし指を突き出すようにして、呼び鈴を押した。そのときに表札が目に入った。
「小高」
と、表札にはあった。はじめて見た。前回は気づかなかった。子宝ロダンの本名は小高なのだ、と、歌うように思った。そうかぁ、コダカなのか。それでコダカラかと思わず笑った。
どうぞという声がインターホンから聞こえ、すぐに玄関ドアのロックがはずれた。
ドアを開けると広めのスペースがある。正面の壁をくりぬくようして飾り棚がしつらえてあるが、そこにはなにも置いてない。
「こんにちは」
と、子宝ロダンが左側の階段をおりてきた。
この前と同じような色のない作務衣の上下を着ている。さっきまで蕎麦を打っていたか、轆轤をまわしていたという風情だ。
「すみません、また来ちゃいました」
圭介は頭をかいた。ロダンについて階段をあがりながら、この前買ったビー玉が出てきたことを話した。
「それが、どうも、彼女のあそこから、みたいなんで……」
ここからの帰り道に神社の賽銭箱に放りこんで、その一週間後に出てきたのだということも説明した。
「賽銭箱かぁ、それはまたすごいところに手放しましたねぇ」
二階にあがると、階段の正面がリビングになっている。リビングの左がキッチンで、階段の右うしろがトイレだということは、前回、覚えた。リビングのまんなかに二メートル近い長さを持つテーブルがひとつと大きめのダイニングチェアが四脚ある。家具らしいものはそれだけだ。
奥の席に座りながら、子宝ロダンは苦笑している。
「賽銭箱になんか入れるから、そういうところから出てきたのかもしれませんね」
ビー玉の出現について、彼はそんなふうに言った。
「そんなこと、あるんですか」
賽銭箱に放りこんだのがよほどまずいことだったかもしれないと思い、圭介は心配顔になる。
「ははは。うそですよ。そんなことはないです。どこに入れたからどこから出てくるなんて、法則はないです……」
「そうなんですか」
「でも、ちょっと、おもしろかったでしょ」
「ええ、そうなんです。ビー玉が出てきて、ほんとに気分が変わったというか……落ちこんでた気分が、すっきりしたっていうか」
「それはよかった」
「美由紀も……おとといまで堕ろすって言い張ってて、きつい顔してたのが、きのうは一日なぁんか機嫌がよさそうなんです。それで、今朝になって、産むっていうのもありだなぁなんて言いまして」
「そうですか」
圭介の買ったビー玉なのに、はっきりと影響を受けたのは美由紀かもしれなかった。どこか吹っ切れたような顔つきになり、それで圭介の気持ちもずいぶんと楽になった。これからどういう展開になるかわからないが、少しずつでも平穏が近づいてくるなら、それがいちばんいいと思っている。
「まぁほんとに、旦那の子どもでもいいかなぁって、そんな気もしてるんですよね」
「ほお」
笑顔をふくらませるようにして、ロダンは大きなテーブルの向こう側にいる。
「誰の子でもいいかなぁって。もともと、そういう関係なんだし、おれと美由紀はね。そうやってはじまっちゃったわけだから」
きのうの美由紀のちょっと明るい顔を見て、圭介はそんなことを考えたのだ。
「彼女が子どもを産んで、ちゃんと離婚しておれと結婚して、おれがその子を育てていけば、その子が誰の子でも、ちゃんと家族かなぁって。そんな気がしたんですよ、きのう」
そういう話をしたくて、今日はこの家に来たのかもしれなかった。
「それで、もしよかったら、美由紀にもビー玉を買ってあげようと思うんですが……いいですか」
ビー玉が入ったガラス容器はテーブルのうえに置いてある。ジャムの瓶をふたまわりほど大きくしたようなガラス製の容器だ。たくさんのビー玉がつまっている。
「どうぞどうぞ」
ガラス瓶に伸ばした子宝ロダンの腕は白い。
その白さを不思議な感覚で圭介は見つめた。けっして不健康というわけではないが、子宝ロダンには溌剌としたイメージはない。
肌は青白く、表情にとぼしい。笑顔か無表情か、そのどちらかしか圭介は見ていない。言葉も腹の底から出てくる力強さはない。なにより、全体の雰囲気が浮世離れしているというか、現実感がないというか。
だから、そのときも、圭介はブログのことを忘れていた。ブログから伝わってくる精力的で辛辣なイメージはまったくないのだ。
「これは、どうですか」
明るい青色のガラス玉を目の前に差し出されて、圭介はわれに帰った。
「いただきます。百円、でしたっけ?」
ビー玉がひとつ百円というのは、たぶん高価だろう。だが、これはふつうのビー玉ではないのだ。
手放しの玉。
なのである。圭介は青い色をしたガラス玉を大切そうに光にかざしてみた。透明のガラス玉のなかに鮮やかな青色の羽根が渦をまいている。
珍しいところのない、ごくふつうのビー玉だ。
「百円なんですけどね」
遠慮がちではなく、子宝ロダンはくっきりと笑った。念入りに練習したようなつくり笑いだ。
「なかには十万とか、百万とか、出すひともいるんですよ」
「は?」
「不思議なことですよ。ただのビー玉、されどビー玉。ひとによってはそれくらいの価値がある、みたいで」
その口調に、圭介は少しだけひっかかった。あやしい匂いが、かすかにした。値段があってないようなガラス玉に百万円を払う人間がいる。それはつまり、お布施とか寄付というような意味合いがあるということだ。
「そんなひと、いるんですか」
と、圭介はとぼけてみた。
「いるんですよ」
子宝ロダンは、今度は、ごく無表情に言った。
「たまに、ですけどね。けどまぁ、百万出したからって、特別なことが起こるわけではないんですよ。みなさんわりと、最初はすぐに出てくるんです。藤森さん、出てきたビー玉、どうしました?」
「ああ、帰りにまた、賽銭箱に入れようと思ってます」
言いながら、圭介はジーンズのポケットに手を入れた。指先がビー玉に触れた。圭介が先週買って、おととい美由紀のあそこから出てきた黄色い玉だ。
「え、また賽銭箱?」
子宝ロダンはちょっと困ったような顔をしている。
「まぁ私、それについては知らん顔してますよ。でね、藤森さんが最初にそれを手放したのが十日ほど前でしょ。それでおとといの夜、出てきた。今度手放すとね、もしかすると、何年も出てこないかもしれない」
「そうなんですか?」
「いや、またすぐに出てくるかもしれない……つまりね、こればっかりは誰にもわからないんでね。もちろん私にもさっぱりわからない。けど、出てきたときは、必ずまた」
と、そこで言葉を切って、子宝ロダンは圭介を見た。
「幸福を実感できます」
顔の前で両手を打つような言いかただった。圭介は目を見張った。
幸福を実感する……そう言えば、おとといの夜の感じもそういうことだったのかもしれない。

「幸福を実感する、かぁ」
と、吐息のように圭介は言った。
「確かに、そんな感じでした」
「でしょう? そうなんですよ、きっとそういうことなんだろうなぁと私、思ってるんですけどね。ただ百万出したからと言って、大きな幸福ってわけじゃないんです。それは、はっきりしてる」
やっぱり宗教じみている、と、圭介は感じた。
祭壇もないし礼拝もしないけれど、これは新種の宗教ではないか。この家を取り囲むコンクリートづくりの建物も、そういう目で見てしまうと、宗教施設のような気がしないでもない。
「子宝教、でしたっけ?」
圭介は、ふいにブログを思い出した。プロフィールにある冗談のような一文を引き合いに出して、いま浮かんだ懸念のようなものを確認しようとしてみた。
子宝ロダンは、おかしそうにうなずいている。
「そうなんです、子宝教……ほんとにぼくのまわりには子宝に恵まれるひとが多いんですよ。きっとね、子どもが欲しいひとを信者にすれば、すごい儲かると思うんだよなぁ。多いですからね、子どもが欲しくて悩んでいるカップルとか」
テーブルに乗せた両手でビー玉のガラス瓶を包むように持ちながら、冗談ではなさそうな口調で子宝ロダンは言った。
「ほんとに儲かると思うんだよなぁ。いつかやりますから、子宝教。そのときは、お願いしますね」
儲かる儲かると何度も言う子宝ロダンに、なにをどうお願いされていいのか、圭介は返答に困った。
「それにしても」
ロダンはしみじみという気持ちをにじませて、首をふる。
「美由紀さんが、産む気になってよかったですよ」
と、笑顔を浮かべた。
「子宝教としては、たいへんおめでたい話だと思います」
などと頭をさげて、
「もうひとつビー玉、買っていきませんか。そうそう、赤ちゃんのためにも、今度は、ひとつ千円で……一万円でもいいけど」
どこまで冗談がわからない口調で語る子宝ロダンに、どういう反応をすればいいのか迷い、圭介はなにも言えずにいた。
ふと、ビー玉で数珠をつくればいいじゃないかと思いついた。ちょっとからかってみたい気持ちになったというのもある。
「そのビー玉で数珠をつくればいいじゃないですか」
と、軽い調子のまま口にして大きな声で続けた。
「きっと売れますよ。ものすごい幸福になりそうだもん」
握ったままの瓶を見つめて、子宝ロダンは首をかしげている。
「それはどうなんだろう……できるのかなぁ」
「あの、それ……ほんとのところ、なんなんですか」
「はい?」
「そのビー玉……手放しの玉とか、なにか謂れがあるんですよね」
「…………」
子宝ロダンは瓶を見て、圭介を見る。ほとんど表情を変えずに、かすかに微笑を浮かべたようだ。
「わからんのですよ、ぼくにも。どうして手放すと戻ってくるのか。戻ってきたときに、どうしてああいう気分になるのか……さっぱりわからないんです」
ちょっとだけ眉をさげて、気弱な感じでロダンは笑う。
「ぶっちゃけ、どこかからまとめて仕入れるんですよね。仕入れたあと、祈祷をあげるとか、やるんですか」
圭介は、宗教じみたことしか考えられなくなっていた。
「ビー玉っていうところが、親しみやすいというか、いまふう、ですよね」
「そうですかね」
子宝ロダンはけっしてうれしそうではない。
彼の背後は天井までのガラス窓になっていて、その向こうに桜の木が見えた。こんもりとした葉っぱ全体がひとつの生きもののように揺れている。九月の昼下がりにしては涼しげな陽射しが窓のあたりできらめている。
「あ、これ、百円」
と、圭介が財布から硬貨を取り出してロダンに差し出した。
「え、ああ、美由紀さんのぶん、ですね」
「すみません、忘れるところだった」
「美由紀さんって、どんな感じのひとなんですか」
とても自然に、子宝ロダンはそう訊いた。今朝はなにを食べましたか、みたいな感じだった。ビー玉から話題をそらしたいのだと、圭介は察した。
「美由紀ですか……あ、そうそう、あいつきのう、気分がいいからって美容院に行ったんですよ」
圭介はスマホを取り出してひとさし指を画面にすべらせながら、
「ばっさりと髪を切って帰ってきたんです。ほんとにご機嫌で。写真に撮ったんですよね」
と言ったあとで、スマホを裏返して子宝ロダンに画面を見せた。
「ほほお」
あごを前に出すようにして、彼は液晶画面を見つめている。
じっとなにも言わずにいるので、画面が暗くなったのかと思い、圭介は画面を自分のほうに向けてみた。胸からうえのアングルで美由紀は思いきり笑っている。
「こんなふうに笑うのも、ひさしぶりなんですよ」
と、圭介は言った。
子宝ロダンは、まるで時間が止まってしまったように動かない。
「子宝さん」
思わず、圭介は声をかけた。
もう一度声をかけようとしたとき、ようやく子宝ロダンは視線を動かした。
「…………」
圭介を見つめて、なにも言わない。
「どうしたんですか」
「いえ、あの、もう一度見せてもらえますか」
「いいですよ、ほら」
画面を見つめる子宝ロダンの鼻のあたりがひきつっているような気がした。困惑したような、ただ驚いているような、とても複雑な顔つきのまま、彼は圭介を見た。
「私、美由紀さんと会ったこと、あります?」
と、子宝ロダンは言った。
「は?」
「ぼく、彼女に会ったこと、ありますかね」
「知ってるんですか」
その偶然に、圭介も驚くしかない。
「どこで会ったんです?」
「いや、だから、それを私も知りたい」
「ぼくにはわかりませんよ。この前も言いましたけど、最初に会ったのが去年の十二月なんです」
「ああ、そうか……」
落胆した様子で、それでも子宝ロダンはスマホを奪い取るようにして画面を見つめる。
圭介はその偶然に驚きながら苦笑するしかない。
「なんだぁ、ロダンさんの知り合いだったのかぁ」
「ちょっと待っててもらって、いいですか」
子宝ロダンはスマホを圭介に戻すと、立ち上がってキッチンのほうに向かった。奥のほうでドアが開く気配がした。裏口から出て行ったようだ。
カンカンカンと鉄の階段をおりる音が、かすかに響いた。
圭介は肩をすくめるしかない。
あたりを見まわして、テーブルに置かれたガラス瓶を手にした。二十個くらいのビー玉は入っていそうだ。何個かもらっていこうかと思ったが、それこそ罰あたりな気がして、やめた。
圭介は改めてリビングルームのなかを見まわしてみた。
真っ白というより淡くくすんだクリームがかった壁。天井も同じように白い。壁に絵がかかっているわけでもなく、本棚が置いてあるわけでもない。とにかく白い壁で囲まれた殺風景な空間のまんなかに、大きなテーブル、そして椅子が四脚置いてある。それだけの部屋なのだ。
だが、不思議と寒々しい感じはしない。
圭介は、窓の外のこんもりと葉を繁らせた桜の大木を見つめて、時間が溶けていくのを感じた。ぼんやりと、子宝ロダンが美由紀のことを見たことがあるかもしれないということについて考えてみた。
子宝ロダンはどこで美由紀を見たのだろうか。もしかすると……と、圭介は確信のようにひとつことを思いついた。美由紀の夫は、以前からそういう趣味があったのではないか。そういう趣味というのは、子宝ロダンのサイトのような志向のことだ。スワップ、輪姦、もちろん、寝取らせなんこともある。そういうことの延長に、夫は妻の美由紀を他人に抱かせることを思いついたのではないか。
そこまで考えて、圭介は一気になにかがわかったような気がした。
どれくらいの時間そうしていたろうか、子宝ロダンが戻ってきた。子宝ロダンのうしろに白っぽい気配が続いて、女がひとり彼のすぐあとに入ってきた。
「すみません、藤森さん……」
と、子宝ロダンがずいぶん弱い声で言った。
「紹介します。海渡先生の奥さん……あ、海渡先生というのはぼくの主治医の先生で……あの、まぁとにかく、海渡佳奈子さんです」
女はやわらかく頭をさげた。思わず声をあげてしまいそうなほど美しい女だった。すっきりと首が見えるくらいのショートヘア。雰囲気はとても落ち着いている。年齢は自分より少しうえかもしれない、と、圭介はとっさに思いながら、ただ見とれた。重くなっていた気持ちは溶けたようになくなっていた。
小さな顔をやわらかく緊張させて、海渡夫人は子宝ロダンのうしろから、気配を探るようにして頭をさげた。
「お世話になっております、海渡でございます」
夫人は、圭介を見て丁寧に言った。圭介は腰を浮かしてお辞儀した。
「あ、いや、ども……」
「実は」
と、声をひそめるように、彼女は椅子をひいて腰をおろした。子宝ロダンもさっき自分が座っていた椅子に腰かける。
夫人が話しだすまえに、圭介は首をかしげ、庭を見た。この家の間取りがどうなっているのかわからないが、海渡夫人はキッチンの奥から現れた。たぶん裏口から入ってきたのだ。ということは、このまわりのコンクリートの家のどれかに住んでいるのだろうか。
「私はこの奥に住んでおります。緑色のが、うちです。いま小高さんがいらっしゃったので、私、慌てて裏口から入ってきました。すみません、突然」
と、夫人は圭介の懸念を察したのか、とてもわかりやすい説明をした。
子宝ロダンのことを、夫人は小高さんと呼んだ。確かに表札には小高となっている。
「主人は精神科の医師をしております」
夫人の声は、意識的なのかひどく事務的だった。
「小高さんは夫の患者さんです」
夫人が言ったことを理解するために、圭介は言葉を反芻してみた。
彼女の夫が精神科医。子宝ロダンはその患者。ということは、子宝ロダンは精神的な疾患をわずらっているということか。
子宝ロダンは無表情にガラス瓶のビー玉を見つめている。
「実は、小高さんは重度の……」
そこで言葉を切ってから、夫人はやわらかく子宝ロダンに視線を送った。子宝はそれに気づかないようにビー玉に目をやったままだ。
「重度の記憶障害なんです。自分のことに関するほとんどすべてを思い出せません」
「記憶障害?」
圭介は心のなかのつぶやきを声に出すような感じで言った。まだ二度しか会ったことのない人間が記憶障害だと言われても、なんのことやらよくわからない。
「重度の……」
気になった言葉が、思わず口から出てしまう。
「記憶障害?」
「小高さんは、自分の出生からいままでの、すべてのことを思い出せないんです。どこで生まれてどこの小学校に行って、とか。中学も高校も、結婚していたのか子どもがいたのか、とか、仕事のことも」
「すべて?」
圭介は目をむいた。そのままあごをひくようにして夫人を見て、それから遠慮がちに向かいに座る男を見た。
それに気づいたのか、顔をあげて、
「そうなんですよ」
と、子宝ロダンは、まるでひとごとのようにくっきりと笑った。
〈4〉
小高正一が本名というのも、少し違う。
小高正一というのは、いまとなりに座っている海渡医師の妻である佳奈子がつけてくれた。海渡医師と佳奈子に会ってからちょうど四年が経過している。その間に、新しい戸籍をつくり新しい姓名を得たのである。
四年前の九月。目を覚ますと、目の前に、大きな男がいた。それが海渡医師だった。医師のかたわらには制服の警察官が立っていた。身元不明者保護というような状況で田園調布警察署から海渡のところに連絡が入ったらしい。
田園調布東に精神科のクリニックをかまえる海渡敬之は、アルコールや薬物中毒の疑いがあったり精神的に障害がありそうな不審者が保護されると、ときどき警察に立ち合いを依頼されることがある。
その半年前に発生した東日本大震災で、東北方面に多数の行方不明者が出ていた。が、多摩川にかかる丸子橋近くで発見された男と、震災との関係はわからなかった。しかも半年もたっている。いったいなにが起きて、なぜ自分が警察署に保護されたのか、まったく不明であった。
はてしなく長く、夢のない眠りから覚めたような心地だった。
ここがどこで、目の前にいるのが誰で、しかも自分がどこの誰なのかさえわからず、とにかく唐突に、そこに世界が現れたのである。
その後、海渡医師がすべての面倒をみてくれた。自宅のとなりに住居を用意してくれ、食事や衣類はもちろん、生活のすべてを援助してくれるようになった。
おかげで、精神状態も落ち着き、一年ほどが過ぎたころ、ようやくひとつのことを思い出した。自分は子宝ロダンという名前でブログを書いていたということだ。
子宝ロダン。
その名前を、はっきりと思い出したのである。ひとつを思い出すと、つぎつぎにいろんなことが記憶のなかから引っぱり出せた。
子宝ロダンのブログをたどってみると「子宝ロダン」の実像も見えてきた。海渡は本人を連れて、関係者の何人かに会いにいった。スワッピングパーティの主催者やアダルトビデオの男優、グッズショップの店長など、いかがわしい人物ばかりだったが、全員が子宝ロダンのことをよく覚えていた。
けれど、誰も彼の本名を知らなかった。
ブロガー子宝ロダンは、実に巧みに自分の素顔を隠していたのである。
そして、そうやって隠してしまった素顔は、とうとう自分からも見えなくなった。どんな家庭に生まれ育ち、どんな学校に行って、どんな仕事をして、どんな生活をしていたのか、すべて思い出せない。
「ずっと前からブログを書いていたことだけ、思い出したんです」
と、子宝ロダンは言った。
広く殺風景なリビングルームで、大きなテーブルをはさんで、子宝ロダンと海渡佳奈子と藤森圭介が座っている。
藤森圭介の不倫相手の美由紀という女の写真を見て、その女のことを知っているような気がした。三年前に自分が子宝ロダンであることを思い出して以来、ブログ以外のものが記憶に結びつきそうになったのは、はじめてだった。
ブログを書くために出会った人物は、つぎつぎに思い出せている。けれど、その美由紀という女は違う。子宝ロダンではないときに、会っているような気がする。が、もしかすると、会ったのではなく、どこかで見かけただけかもしれない、と、靄のような感覚が頭のなかにひろがっていく。
「でも、あれ……あれじゃないですか」
圭介は、声が裏返りそうになるのをこらえながら、言葉を探しているような顔つきで言った。
「ブログが残っていたなら、サーバへのアクセス情報とか、いろいろと個人情報も確認できるんじゃないですか」
と、ロダンにではなく、佳奈子に強い視線を投げる。
こんなタイミングで記憶障害のことを聞かされて、彼にも迷惑な話だろと子宝ロダンは思った。それでも強い関心を持ってくれるのは、やはり、記憶障害という疾患にインパクトがあるからだということも、最近わかりかけてきた。
「ブログのページはそのまま削除もされずに残っていたんですが、サーバへはアクセスできませんでした。パスワードもなにも忘れてましたから」
子宝ロダンは、説明書を読むように言った。そのあたりのことは、ブログの関係者に会うたびに口にしてきたことなのだ。
「それで……これもまた海渡先生の知り合いのかたにお願いして、新たにブログを立ちあげたんです。内容はほぼそのままにして。先生も、治療に役立つかもしれないから、続けましょうって……」
となりで佳奈子はなにも言わなかった。
目の前で佳奈子を見つめる圭介は、視線をはずせないでいるようだ。そのことが子宝ロダンにはよくわかる。
自分にも、佳奈子の美しさは充分すぎるほどにわかるのだ。
あんな内容のブログを書いている子宝ロダンと、美しい人妻。そんなふたりを前にして、たぶん、いま、圭介はいろいろなことを妄想しているに違いない。
その妄想について、たぶん佳奈子は気づいている。
それはとても、妖艶な一瞬だった。

「でも、そんな……」
と、まわりの空気をひっかきまわすような素振りで、圭介は視線を子宝ロダンに戻した。
「記憶喪失なんてことが、ほんとにあるなんて……」
その言いかたは、ため息のようだった。しばらく窓のほうを見てから、圭介はひどく遠慮がちに声をあげた。
「美由紀を……」
と、圭介はロダンを見た。考えていたことを確認するような顔つきだった。
「ロダンさんが、美由紀を取材したってことなんですかねぇ」
言いながら、圭介はあえぐように苦笑した。
「どこかのスワップパーティに出ていたとか……旦那が昔からそういうことが好きで、みたいな」
「ああ……」
ロダンは、圭介の言葉の意味に気づいて、小さく首をふる。
「どうも……そうではないと思うんですよ。そういうところで会ったのではない感じがして……だから、あの、ちょっとぼくも困っているというか……」
「ああ、なるほど……」
圭介は少しだけおだやかな微笑を浮かべると、軽く首をかしげて、
「じゃあ、美由紀に会ったのは、いつぐらいの話なんでしょうかね」
と、言った。
「たとえば子どもころとか、数年前とか」
そう訊かれても、ロダンは同じように首をかたむけるしかない。
「子どものころって感じではないです。そんなに前じゃない……と、思う」
つぶやく目つきが、はかないほど頼りない。
「美由紀さん、でしたっけ?」
と、佳奈子が小さく声をあげた。
「髪をお切りになったとか……」
彼女に向かって、圭介はひどく真剣な表情を浮かべる。
「そうなんです。きのうです。すごく気分がよくなったって言って」
「そういう髪型は、はじめてですか」
「さあ、わかりません。ぼくがはじめて会ったのは去年なので……そのときは、肩くらいだったと思います」
黙ったまま、ロダンは腕を組んでいる。
とりとめのない沈黙が、テーブルのまわりに広がった。
「すみません。みょうなこと言いだして」
と、息を抜くように、ロダンは弱く詫びた。
「いえ」
圭介は、首をふった。
「でもきっと、美由紀は子宝さんとどこかで会ってるわけですね」
「それも確かじゃないんです。どうもそんな気がするってだけで」
「聞いておきます、美由紀に」
圭介はまるで決意を口にするみたいに、佳奈子を見た。
「こんなひとを知ってるかって……なんなら、一度、ここに連れてきますから」
「ぜひ、そのときは、よろしくお願いします」
佳奈子は遠慮がちに頭をさげる。
「いやぁそれにしても」
と、はじけるように圭介は背筋を背もたれに押しつけた。
「そんな、記憶障害なんていうのが、ほんとにあるんだなぁ」
さっきから圭介は何度もそう言っている。けれど本人は気づいていない。それほど関心があるのか、懸念があるのか、とにかくどこか不可解な話だと思っているのだろう。
「とても珍しいことのようです」
海渡夫人は、少し悲しそうな目をした。
「主人は、日本ではきわめて珍しい症例ではないかと言ってます。重度の記憶障害というのは、実例を見たことがないらしく……」
圭介はその口調に押されるように、黙った。
「申しわけないのですが……」
海渡夫人は、そう言ってから、やわらかく圭介を見た。
「いま主人にも連絡しましたが患者さんもいらっしゃるので、すぐには戻ってこられません。本来なら主治医からきちんとお話しすべきところですし、できれば美由紀さんにもお会いしたいはずですが……ほんとうに、申しわけありません、今日のところは、いったんお帰りいただいてもよろしいですか」
佳奈子は子宝のほうに目をやる。
「小高さんにも、安静にしておいて欲しいので……」
圭介はすぐに納得して腰をあげた。
「そうですね、すみません、じゃあ、ぼくはこれで……」
「ごめんなさい、わざわざ来てもらったのに」
ロダンもテーブルにすがるようにして立ちあがった。それに向かって、圭介は慌てたように腕を伸ばす。
「いや、いいんです。とんでもない、休んでてください。また来ますから、今度は美由紀を連れて……」
などと、ばたばたとした感じで階段に向かう。
「どうもありがとうございます」
玄関ホールで、海渡夫人が丁寧に頭をさげた。そのうしろから階段をおりてきた子宝ロダンもかたく笑いかける。
「じゃ、どうも、失礼しました」
と、藤森圭介はそんなふたりに手をあげて、なぜか困ったような顔つきでドアを閉めた。
そのあと、ホールで子宝ロダンは佳奈子の目を見た。
なにも言わず、佳奈子は少しだけ首をかしげる。そして、小さな呼吸のあとで、
「思い出せると、いいですね」
と、笑った。
「ええ、まあ」
子宝ロダンには、それしか言えなかった。
圭介は、通りを五メートルくらい行ったところで大きく振り返った。
四角い箱のようなコンクリートの建物が、色をわけて四つ置かれている。オレンジと緑と濃紺と赤。大きく枝を広げた桜の木に抱かれるように配置された四角い箱の、もっとも手前にあるのが子宝ロダンの家だ。
「なんだか……」
ちょっと肩をななめにして、くちもとも同じようにゆがめて、圭介は吐き捨てた。
「あやしいじゃん」
重度の記憶障害って、そんなの……と、そこで思考は止まってしまう。さっき海渡夫人が言ったように日本では珍しい症例のようだが、そんな話がほんとにあるのかどうか、圭介には確信が持てない。フィクションの世界ではありそうだが、現実にそんなことがあるのだろうか。
(それにしても……)
と、圭介はオレンジ色の家に背中を向けて歩きだしながら、しびれるように思った。
(いい女だった)
佳奈子である。和服を着てどこかの旅館の女将でございますなどとテレビで紹介されたら、間違いなくその旅館に客が殺到するだろう。そういうレベルの女だと、圭介はなんの根拠もなくぼんやりと思う。
とにかく、いい女だった。
そう思い、改めて子宝ロダンのブログを思い出してみる。夫婦交換とか3Pとか乱交とか、そういう話題のなかに佳奈子という女を置くと、なにやらとても興奮してくるではないか。
「やっばいなぁ」
小さくつぶやいて、圭介は大きく振り返った。
オレンジ色の家はもう見えなかった。
けれど、大田区東雪谷の高級住宅街に、とても妖しい人間たちが住んでいるのだけは確かだと、圭介は少し昂ぶった気持ちで思った。
〈5〉
その日の夕刻、海渡敬之は急いで戻ってきた。
それでも六時をまわってしまった。彼は、玄関のドアを開けてリビングに入り、ひとの気配がないことを確認しながらソファに鞄を置き、長い廊下を通って裏口から出た。
娘の美結はこの時間ピアノのレッスンに行っているはずだ。小学校から帰宅せずにそのままピアノ講師の自宅に出向く。自分にも妻にも音楽の素養はないと思うのだが、幼稚園のときに本人がビアノを習いたいと言いだして続けているのだ。
中庭を抜けとなりのうちの裏側にまわると、白い螺旋階段をあがった。コンコンと、鉄製の階段は高く鳴った。
小高正一の家のキッチンは二階にある。海渡は螺旋階段をあがりきると、キッチンのドアノブに手をかけた。鍵はかかっていない。ドアをひくと、黒いゴムサンダルのとなりに佳奈子の小さなサンダルがあった。
こじんまりとしたキッチンのガスコンロの上で薬罐が湯気をあげている。それを横目で見て、海渡は奥のリビングルームにつながる引き戸を開けた。
大きめのテーブルの奥に正一が座り、ぼんやりとビー玉の入った瓶を見つめている。
そのななめ手前に妻の佳奈子が座り、入ってきた海渡を見た。
「おかえりなさい」
「うん、遅くなった」
海渡はずいぶんと大袈裟に表情をひきしめている。大きな男だ。
夫の運んできた緊張した空気をなごませるように、佳奈子がやわらかく腰を浮かせながら笑いかけた。
「コーヒーでいいですか」
「ん? ああ……」
海渡敬之は四十五歳だが、筋肉のよくついたがっちりとした体型している。毎週ジムに通っているのだ。
「すみません、先生」
と、正一はいつもと同じように、不思議な間合いのあとで笑った。その笑顔にうながされるように海渡は椅子に座り、少し背中をのばした。
「聞いたよ。佳奈子から連絡があった。会ったことがありそうなんだって?」
海渡の声は低く、張りがある。
「さあ、しっかりと話してごらん」
催眠術師の声色で、海渡はそう言った。自分の心のなかを、できるだけ正直に言葉にしたくなる、そういう声のトーンとリズムとスピードを、長い経験から身につけているつもりだった。
「はい」
正一は、いつものように、海渡の声にあわせて、おだやかな表情になった。
「先週、ここに来た男のひとがいます。藤森圭介さん。年は確か、三十六歳だったかな。彼は独身ですが、よその奥さんと不倫をしています」
「…………」
海渡は目だけでうなずいてなにも言わない。
「その人妻は、美由紀さんという名前です。その美由紀さんの写真を、今日、藤森さんが見せてくれのです。きのう髪を切ってスマホで写真を撮ったと言って……そのひとを、ぼく、見たことがあるんですよ」
「美由紀さん、だっけ?」
「そうです。花岡美由紀さん……」
「ふーん……で?」
さっきから姿勢を変えないままテーブルのうえに肘をのせて、海渡敬之は正一のことを見ていた。
「ブログを書くプロセスで会ったわけではないんだね」
「ええ、たぶん。それも、会ったかどうかわからないんです。でも、知っている気がする」
「そうか。それは貴重な話だね。で、どんな感じがするの?」
子宝ロダンにそんなことを質問するのは、はじめてのことだった。彼が子宝ロダン以外の記憶に関する断片を語ったことはない。
「どういう感じ?」
正一の視線は弱々しく揺れている。
「その女のひとが、記憶のどこかに引っかかってている感じがしたわけだよね。その感じ、だよ。たとえば、すごく親しいとか、やわらかいとか、やさしいとか……」
「いやぁ」
正一は首をふりながら頭をかいた。
「それは、わからないですねぇ」
と、かすかに笑う。
「でも、感触があるんですよ。会ったことがあるのか、それともどこかで見かけたことがあるのか……うまく言えないんですけど、このひとを知ってるって感触なんです。思い出せてるわけじゃない。あくまで、そんな感触……」
正一はさっきからずっと考えていたことを、ようやく言葉にしていた。迷いながらの確信は、せつないくらい淡く希薄だ。
「感触かぁ」
海渡医師は表情を変えない。
そのとき、海渡敬之には、いつものように自分の仕草や表情をコントロールできているか自信がなかった。
ひとことで言うと、少しばかり動揺していたのである。
だが、ふだんの職業的なふるまいのおかげで、無表情のまま平静を装って背もたれに体重をかけていることはできているはずだ。
解離性同一性障害で本来の自己に戻れていない子宝ロダンが、今日の昼過ぎに来た男が見せた写真の女を覚えていると言いはじめた。
はじめてのことだった。
精神科医の海渡敬之が、主治医として継続的に観察を続けたなかで、はじめてのできごとなのは間違いなかった。

海渡敬之が、その身元不明者に会ったのは四年前だ。田園調布警察署から電話がかかってきて夕方面会に行った。そういうケースはよくある。薬物中毒やアルコール中毒、精神的な錯乱状態など、警察から協力を求められることは多い。その日はたまたま診療が終わり、帰宅する準備をしていたので、そのまま田園調布警察署に立ち寄った。
その男は、まったく無表情のまま、警察署のすみのパイプ椅子に腰をおろしていた。
それが、子宝ロダンだった。
もちろんそのときは、彼は子宝ロダンでもない、ただの「真っ白な男」という状態だった。
重度の記憶障害というのは数か月診察を続けたあとで出した診断結果だが、警察に保護されたばかりの様子は「真っ白」と表現するしかなかった。
こちらの問いかけや周囲の音などの刺激に反応を示さない。が、やはり空腹は感じるのか、警察官が用意してくれたサンドイッチは食べた。
原因はPSTD(心的外傷後ストレス障害)だと警察には報告しておいた。震災の混乱で、それまで日本ではあまり報告がなかった事例がたくさん出現していた。恐らく、彼も震災のときに想像を絶する衝撃的な体験をして、それが原因になって解離性健忘を発症し、記憶をなくしている。それが海渡敬之が警察に提出した診断書のあらすじだった。
それから、長い治療がはじまった。
海渡敬之は、自分の家のとなりに彼を住まわせることにした。
その三年ほど前に、祖父の代から建っていた古い家を取り壊し、広い土地を区切って四軒の家を建て、一軒に自分たちが住み、ほかを貸していた。まだ娘は生まれておらず、妻とのふたり暮らしでは、以前の土地は広すぎたのである。
道路沿いの一軒が空いていたので、そこを男の住まいにした。
男はその家で少しずつ落ち着き取り戻し、一年ほどたったときに、自分が子宝ロダンという名でブログを書いていたことを思い出した。そこから、つぎつぎと彼は「子宝ロダン」に関することを思い出すようになった。出会った人物、遭遇した出来事、そして、子宝ロダンとしての自分自身。
そういうふうにアイデンティティが確立されれるにつれ、精神状態はとても安定してきた。
奇妙なほど子宝ロダンに関する記憶は強固で鮮明なのだが、それ以外は、まったく思い出せないままである。よほど強い精神的なブロックがかかっているに違いなかった。
「あまり無理しないほうがいいよ。思い出せないってことは、思い出したくない理由があるということだからね」
海渡は、何度もそう言って、子宝ロダンを安心させようとした。
それが今日、突然、子宝ロダン以外の記憶に触れる人物が現れたのである。
「それは大きな進歩だ」
妻からクリニックに連絡があったとき、海渡は電話機に向かってふるえるようにつぶやいた。佳奈子は、海渡以上に深刻にそのことを予感していたようだ。
トレイにカップを三個のせてリビングに戻ってきた佳奈子の表情を見て、海渡はおだやかな目をした。
コーヒーの香りがリビングに漂う。
「きみは、その女のひとの写真、見た?」
海渡の問いに、佳奈子は小さく首をふった。
「見たけど……」
彼女が写真を見たからといって、なにかが判明するわけではないことは明らかだ。だから海渡も問いつめもしないし、佳奈子もあまり気にかけている様子はない。
「私、少し、心配……」
それでも、佳奈子はそんなふうに言いながらカップをテーブルのうえに置いた。
「いま聞いたら……」
佳奈子は眉のあたりに影をつくったまま、正一の白い顔に目をやる。
「少し気になることがあるので、出かけたいなんて言うし」
ほんのささやかな棘のようなものが、その言葉のあとにちらついている。
「気になること?」
海渡は佳奈子を見て、正一を見る。
正一はおだやかに微笑を浮かべ、肩をすくめた。
「ぼんやりと……引っかかることがことがあって」
言いわけのような表情を、正一はした。
「ちょっと出かけようと思うんです」
「その、女のひとに会うにいくのかい」
できるだけふつうに、海渡は訊いてみる。
「いえ、べつのひとなんです。けど、どうも、美由紀さんと関係がありそうな気がして……よくわからないんですけど」
と、これもまた平然と答える正一を、佳奈子はきつい目で見た。
「そんなに、あせって出歩かないほうがいいと思うんだけど」
「それは関係ないですよ、ねぇ」
正一は甘えたように海渡に顔を向ける。
「うん、まぁな」
海渡にはそう答えるしかない。
とにかく、動きはじめたと考えるのがもっとも適切だろう。
はじまったのである。
子宝ロダンという人物が、いよいよ、子宝ロダンとして動きはじめた。
不思議な話なのだ。
あまりに不可解で、謎だらけの話。
その謎にうろたえている間もなく、今日、過去に出会ったことがあるかもしれない女の写真を見たと言う。
海渡敬之には制御不能な、なにかが起りつつある。
目の前に座る気弱そうな男が、これから、巻きこまれるであろう出来事。
胸のなかにかすかに不安を感じながら、できるだけおだやかに、あえて胸を張って、海渡は妻に笑いかけた。
「大丈夫だよ」
その言葉に意外に大きく反応したのが、正一だった。そうですよね大丈夫ですよ、と、彼は佳奈子を見て笑った。

