子どものこころを
まんなかに
5. 病気と死

子どもは、まず親の死を恐れる
「明治大学 子どものこころクリニック」院長の山登敬之さんとの対談。今回のテーマは「病気と死」。いやぁむずかしそうだなぁ。とはいえ、子どものときの病気とか死に対するイメージは、ひどく抽象的なかたちで恐怖と結びついている気がする。その抽象性を子どもなりにどう受け止めるのか、なんてあたりも大切な話になりそうである。
とかなんとか、六十歳を過ぎた男ふたりが話していると、ついつい、自分たちの病気とか死についての語りで熱くなってしまうのであるが、それこそ、ここで「子どものこころ」という視点を持ちこむ意味だという気もするので、とにかく、話を進める。
〇
山登「子どものころに、死を考えて怖くなったみたいな記憶はない?」
松尾「それは、自分のことより、親ですよね」
山登「親だよね。幼稚園くらい?」
松尾「すごくよく覚えているのは、エピソードではなく……悪いことって不意に起こるでしょ?」
山登「はいはい」
松尾「いきなり親がいなくなっちゃうとか、帰ってこないとか、事故で死んじゃうなんていうのは、不意に起こる。だから、不意に起こらなくするには、考えておけばいいんだと。つねに自分のなかで予測していると、それは起こらないんだと思って、一生懸命、親が出かけるたびに、この人はもしかしたら死んじゃうかもしれないと思ってた」
山登「へえ。それはいくつくらいのときの記憶なの」
松尾「小学校低学年くらいかなぁ。幼稚園とかじゃなかった気がする。小学生くらいの記憶」
山登「ふだん考えてればって言っても、考えてられないじゃん。やっぱり」
松尾「考えてられない」
山登「いつの間にか、そういうことが終わっていく。知らない間に終わった?」
松尾「ふと気になるときに、そんなことを考えるのをやめようと思うんじゃなくて、逆にそこはきっちり理解しておこうと一生懸命考えて……理解なんてできないんだけど」
山登「心構えみたいなもんだね。備えあれば憂いなし。子どもが親の死に備えられるわけはないんだけど。子どもなりに一生懸命考えてるんだね」
松尾「ふつう、子どもって考えちゃうでしょ、親の死について」
山登「考えるもんですよ。だから、おれも自分が死んだらっていうのと、親がいなくなっちゃったらどうなるんだ、みたいなことを考えて怖くなったっていう覚えはある。けど、それで、ひとりで頭を抱えて悩むみたいなふうにはならなかった。なんとなく考えてて、それを誰かに話してもいないだろうし、知らない間に気にならなくなったみたいな。みんな、ふつうに健康な人間は、そういう過程をたどるんじゃないかな」
「備えあれば憂いなし」。そういう言葉を子どものときに知っていたわけではないけれど、たぶん、そういうことだったのだろう。が、実際には、もっと子どもっぽい発想だった気もする。「死なない」とか「病気になんてならない」なんて安心していると案外そうなっちゃったりするものだから、逆に「死ぬぞ」「病気になるぞ」と想像しておけば、そうならないんじゃないか、と。
うまく説明できないのだが、子どもは、そうやって、あれこれと恐怖のイメージと闘っているということかもしれない。
山登「うちはね、3歳のときに祖父さんが家で死んでるんだよね。病気で療養してた祖父さんだった。当時は3世代同居なんて当たり前だったから、そんなふうに身内の死に接する機会もあったけど、いまの子たちって、あまり身近に死はないよね。学校の友だちが死んじゃったりとかいうのは、あった?」
松尾「ないんですよ」
山登「3歳でお祖父ちゃんが死んだとき、うちで葬式やって、霊柩車が出ていくときに、従兄がおれを背中に背負って霊柩車を追っかけてくれたっていうのは覚えてるんだけど、それがきっかけで死がたまらなく怖くなったっていうことは、ぜんぜんなくて……もっとべつ文脈で親か死んじゃったらどうしようみたいなことだったと思うんだけど」
松尾「それとこれとはべつなんだね。誰かの死を体験すると、怖くなくなるっていうことは、ない?」
山登「どうだろうね、免疫ができるみたいな?」
松尾「免疫というか、ひとつ理解できるみたいな」
山登「ああ、人間は死ぬんだなっていう……死んで、みんなが悲しんで、お葬式という儀式があって、みたいな? そういうことは学習するのかもしれないね」
〇
私のまわりには、あまり「死」とか「病気」が具体的なかたちではなかった。だから、強烈に意識したことはないので、よけいに、概念として抽象的すぎるというか……だから、「鬼が来ると思っていれば、実際には来ない」というような幼児的なまじない感覚でいられたのかもしれない。
家にネズミがいた話

山登さんと「病気と死」について話そうと決めて、ぼんやりと自分の記憶をたどったりしている時期に、わが家にネズミが現れた。小さな黒いクマネズミ。ふと窓の外をみると、そこに置いてあるオリヅルランの葉っぱの上に、ちょこんと黒いネズミがいた——。
わが家の構造を説明すると、私の部屋は地下室になっていて、窓の外がドライエリアという名の空間である。床の中央に雨水などを貯めるタンクがあり、すみっこにエアコンの室外機が置いてある。上部はグレーチングという柵のようなフタ。もしかすると、ネコに追われてグレーチングの柵から落ちてきたのかもしれないが、とにかく、そこにネズミが現れたのである。
ネズミは、しきりに上を見つめて、覚悟を決めてオリヅルランの葉っぱから壁にジャンプする、が、引っかからずに落ちる。
床を走りまわっては、ほかの鉢によじのぼり、上を見て、またジャンプ。それを繰り返している。
大きな窓の向こうでネズミを飼っているような状態なのである。とにかく、そのネズミがほかに逃げられるところは、ない。
松尾「どうしたらいいだろうとカミさんに話したら、トングとかでつまんで逃がすのはやめてくれって言うわけ。途中で部屋のなかに落ちたりするのはいやだから。それでまぁ、とにかく処分するしかないと思ってドラッグストアに行ったのね。いまは、毒のエサみたいなものは、ペットが食べるとまずいからか売ってなくて……あったのは、紙製のネズミ取り。A4くらの段ボールの紙が2枚入ってて強力粘着テープみたいになってて、ネズミの通り道に置いてくれと書いてある。紙は四角いトンネルみたいに折れるから、そうすると、隅っこに置きやすいと」
山登「ゴキブリホイホイみたいな」
松尾「そうそう。で、説明書を読むと、これには薬剤として毒物は入っていませんと。要は、ただのトラップ。仕方ないから、それを仕掛けたわけ。2個入り。そしたら、翌日、見事に捕まっちゃったのね。筒のところから尻尾だけ出てる。覗いたら、いるわけですよ」
山登「そのときはもう死んでたの?」
松尾「と思う。動かないから。でも、きっと、ああいう小動物は動けなくなると生体機能が低下して仮死状態みたいになると思うんだよね。説明書を読むと、捕まったら生ゴミで捨ててくれって書いてある。しょうがないから紙袋に包んでガレージにところに置いておいて、2〜3日後のゴミの日に出した。それはそれでいいんだけど、この年齢になって体験した身近な死になっちゃったの。すごくこう……罪悪感」
山登「自分で手をくだしたわけだもんね」
松尾「そうそう。トラップにつかまったまま動けないってちょっと残酷な感じもするし。毒のほうが安楽死だったんじゃないか、とかさ。でも、不思議なもんで、ゴミの日を過ぎると、その気持ちがちょっとラクになったりして……」
山登「まあね、そこにいなくなるから」
松尾「子どもにとっての死を考えながら……この年になっても気持ちがいいもんじゃないなぁって思った」
山登「子どものときって、そういう小動物を飼っていて、死ぬと庭に穴を掘って埋めたりして、なんとかの墓とか木の札なんか立てたり……」
松尾「そういうペットの死を体験して穴を掘って埋めたりするのが、いい体験になるとかよく言うじゃない? 実際どうなんですか」
山登「生きものは死ぬんだっていうことはさ、さっきの話じゃないけど、子どもなりに、悩めるところまでは悩むわけじゃない。真剣に考えてご飯が食べられなくなっちゃう子も、なかにはいるかもしれないし……」
山登「今回のコロナなんかも、毎日テレビで報道されて、今日の感染者が何人、死者は何人みたいな……ああいうのは、感じやすい子にとっちゃあ、けっこうキツいんじゃないかな」
松尾「知らないことやわからないことがあって、親に聞いたり自分で調べたり、友だちと話して理解できることはあるけど、死っていうのは、恐らく、ぜったいに理解できないでしょう?」
山登「そうだね。どう教えていいかわからないしね」
松尾「ペットが死ぬとか、マンガとかドラマのなかでの死とか……抽象的なものとして理解していく……トラウマってことにもなるの?」
山登「それは、どういう体験かによるね。自分だけで死体を発見しちゃうとかさ、そんなことになったらたしかにトラウマだろうけど……そういうことを言えば、原爆記念館を修学旅行のコースに入れてたら、親が子どものトラウマになるからやめてくれとクレームを入れた話とかなかったっけ? だけど、ああいうのはしっかり教えておいたほうがいいと思うんだよね。非常に感じやすい子は、希望を聞いて無理に見せないって方法はあるにしても、まるまる、はずしちゃうのはよくないよね。これは、まあ、死がどうのってより平和教育の話か……」
〇
飼っていた犬とかペットが死ぬ。そういうとき、身近に死を感じる。私がこの年齢で体験したネズミの死は、私自身が生命を奪ったわけで、みょうに生々しい少しばかりの罪悪感もあった。
ちなみに、カミさんは、その騒動の夜に「クルマに乗っていて、そのまま海に転落して脱出する夢を見た」と言う。
「精神的に、あれこれ、関係しているんだよ、きっと」
などと、自分たちの心のなかに引っかかっている「ネズミ問題」について話したのである。
重い病気の子どもの気持ち

松尾「もうひとつ、きょうのテーマとしては病気っていうのもあるんだけど……それはもっと身近に、親が病気でとか、寝たきりとか……」
山登「病気については、自分も病気になるわけだからね。風邪からはじまって、ちょっと入院するような病気になるかもしれないし。それはそれで、子どもにとっては、大事な体験なんじゃない? だって、自分は、生きものだっていうことを実感するのは、そういう病気を通してっていうこともあるでしょう」
松尾「入院してなきゃいけない子もいるよね。ああいう体験をすると、精神的に強くなるとか、そういうことはあるんですか?」
山登「強くなる……どうだろうねぇ。関係はあるとは思うけど。その子にしか味わえない体験だから……。
昔、おれは子どもの病院にいたんで、毎日病棟で重い病気の子に会ってた。そこには、たとえば腎臓病で血液透析とかやってる子がいるわけよ。血液を体から取り出して装置に循環させてきれいにしてから戻すんだけど、まず腕や脚で動脈と静脈をつなぎ合わせてシャントをつくる。それに針を刺して血を抜く。でも、そのシャントって、手脚1本あたり4年ぐらいしか持たないんだって。いまはどうか知らないけど、当時はね。だから、手脚が4本あるとして、全部で16年、シャントがおじゃんになったら透析ができなくなるから、それがイコール寿命。透析やってる子たちは、それを知ってて「あたしは、あと12年」みたいなことを言うわけよ。そういうことを冗談っぽく、小学生が話したりしてるわけ。
ちっちゃいころに病気になって、闘病生活続けている子のそういう感覚っていうのは、軽い病気でたまたま入院してくる子と違うと思うんだよね。死がもっとリアルで身近っていうか……。先天性の心疾患で二十歳まで生きられないって医者に言われたとか、そういう子も入院してたよね。親はそんなこと子どもには伝えないだろうけど、子どもは毎日病院で生活してればなんとなくわかるだろうし、自分の死も考えざるを得ない」
松尾「それは山登先生が様子を見に行くわけ?」
山登「精神科のベッドは慢性疾患の病棟にあったんだよ。おれはその子たちの主治医じゃないんだけど、話してる様子をそばで聞いてたりしてたんだ。
いま話してて思いだしたけどさ、白血病で、おかしなこと言い出した子がいるから診てくれってんで、小学生の高学年くらいだったかな……見に行ったらさ、ちょっと興奮状態みたいになってて、タオルに水をかけたり薬品かけたりして、自分のクローンをつくります! とか言ってんの。あとからお母さんに聞いたら、自分の分身をつくって、親に残してこうとしたんじゃないかって言うわけ。設計図みたいなのを描いて、クローンだかロボットだかつくろうとしてた。退院しておうちに帰れる当てがはずれて、わーってなっちゃったのかもしれないけど、確かに、死を意識して、自分の分身を親に残していくつもりもあったのか……」
松尾「分身を病院に置いて自分は帰りたいとか? 家に帰りたかったんだよね」
山登「家に帰りたかったんだよ。帰りたかったのに、病気が悪くなったからダメだって言われちゃって……。気の毒にね、その子、その半年後くらいに白血病が治らずに死んじゃったんだよね。お母さんは、その子が亡くなってから思い出話みたいに聞かせてくれたんだけど」
有名人の死、友人の死
松尾「今回、病気と死っていう項目を立てた山登先生の思惑のなかでは……大きなテーマではあるだろうという感じなの?」
山登「それはだって、子どもだけじゃなくて、人間の永遠のテーマだからね。子どものころから、たぶん、みんな気づいていて、一時期そのことを深刻に考えたり、悩んで具合が悪くなっちゃったりして、でも、なんとなくまぎれていって、おとなになって日々を生きてるみたいな。おりに触れて、身近な人が亡くなったりとか、あるいは自分の好きなアーティスでもなんでもいいけどさ、ショックを受けたりとかもするわけじゃない。だから、子どものころからずっと、自分の死にいたるまで、そのテーマは、続いてるわけだから」
松尾「山登さんは有名人の死で、いちばんショックだった人は誰?」
山登「それなんだけどさ……たとえば、大学のころは演劇やってたから、つかこうへいが大好きだったけど、死んだからって、ぜんぜん動揺しなかったんだよね。自分が傾倒していた作家やアーティストが死んでも、そんなにね。だって、実際に会ったことないし……。コロナで志村けんとか亡くなってさ、あれですごくショックを受けた人もいるわけでしょ。でも、もとから関心ないっちゃあないし(笑)」
松尾「まぁただの有名人って感じ……」
山登「うん。松尾くんは?」
松尾「ぼくはスティーブ・ジョブズかな」
山登「あれはいつごろだっけ?」
松尾「50代で死んで、もう10年くらいたつんじゃないかな。ジョン・レノンは、ぜんぜん心には、来なかったんですよ」
山登「はいはい」
松尾「はじめて、ジョブズの死は、偉大な人が亡くなったって、ちょっとしたショックだった」
山登「たとえば昭和天皇が死んだとかさ。ああいうのでも、すごくこう……揺さぶられる人は揺さぶられるんだろうね。あれはほんとに一大イベントだったけれども……あの人が死んだっていうことよりも、時代が変わるなみたいなのはちょっとあったかもしれない」
松尾「自分のなかでの昭和みたいなのがあって、それが大きく変革するというところの……」
山登「でも、さすがにね、身近な人は……たとえば、昔の友だちとかさ、亡くなると、この年になるとちょっと違うよね、やっぱり……昔よりも敬虔な気持ちになるというか……」
松尾「ひとごとじゃないっていう……ちょっとは自分に影響してるからかしらね」
山登「有名人っていうのはさ、直接関わりがない。感慨深いものはあるかもしれないけど、こちらの精神生活がどうこうっていうほどショックは受けない」
松尾「そうね」
山登「それはちょっと自己愛の問題かもしれないけどさ。やっぱり自分がいちばんかわいいっていうのが強固にあるのか、あんまり揺さぶられないよね」
松尾「あるある。誰かのお葬式とか、誰かが死んだっていう……ぼくは、お葬式もあんまり行かないタイプなんだけど……行かないですむなら行かないタイプ」
〇
そう言えば、と、葬式の話をしていて、ふたりの友人のことを思い出した。大学時代の同級生と後輩で、そんなに遠くない以前に、3人で食事をしたことがある。それから数年後に、後輩が亡くなった。その葬式の席で、もうひとりの同級生も亡くなっていたことを知ったのである。
松尾「あの食事をしたときの、3人のうちのふたり死んだということはね、なんだろうと思った。そのときにおれが考えたのは……あのふたりは、わりとネガティブ思考だったと」
山登「はぁはぁ」
松尾「なんかね、その3人の違いを言えば、おれひとりでポジティブシンキングで、このふたりは、ほんとにちょっとね……発想がうしろ向きというか。だから死んじゃったんだと思った」
もちろん、それはまったく勝手な「こじつけ」であり、科学的な根拠はなにもない。本人たちの性格をきちんと把握しているわけでもないし。ただ、あの瞬間、いっしょに食事をした3人のうちふたりがいなくなって、自分だけが生きている——その理由など考えても仕方ないのだが、きっと、私自身、なにかに怯えたのだと思う。
山登「でも、よく言うじゃない、ポジティブ思考のほうが長生きするみたいなさ」
松尾「ポジティブにものごとを考えるってことは、ちょっとトラブルが起こっても、それは大丈夫だよって、根拠ないかもしれないけど……たとえば、がんですよって宣告されても、ポジティブだと、なんとか克服できるかもってあれこれ調べたり学んだり、こういう精神状態のほうがいいんだって思ったり、明るく生きていよう、歩けるなら歩こう、みたいなふうになっていく気がするんだけど、ネガティブな人だと、ああもうダメだダメに違いないって……」
山登「そうそう」
松尾「生命力が弱っていくよね」
山登「笑ったほうが、免疫力があがるとか寿命が延びるって、よく言うじゃん」
松尾「言いますねぇ」
山登「それは、その人の気質でもあるし、養われた性格でもあるんじゃない。前に話に出た、日本の子どもは幸福度が低い。ということは、これから、平均寿命がだんだん縮まっていくかもしれないね」

60歳を過ぎて考える
病気と死——子どものこころを中心にあれこれ考えたいのだけれど、60歳を過ぎた私としては、ひどく具体的に自分の問題として浮かびあがってくる。子どものころのイメージを想像するより、これから先、現実的に訪れるであろうイベントとしての意味のほうが大きくなってしまうのだ。子どもにとって「病気と死」はなにか、なんて考えてる場合ではないってことかもしれない。自分の問題なのだ、切実に。
〇
松尾「120歳まで生きるらしいじゃないですか」
山登「ああ、そうなの?」
松尾「そうなのって医者に言われると自信なくなるけど……ほんとは120歳までは生きるようにできてるらしい、人間のからだは。120になると、確実にいろんなものが枯れて終わっちゃうんだという話」
山登「人間のからだは大事に使えば120まで持つってこと?」
松尾「そうそう。120より生きるってことはないんだけど、がんばれば120までは持つようにできていて、だとしたら、どうせなら120まで生きてやろうと最近思ってるんだよね」
山登「ほおほお。糖尿病は大丈夫なの? 最近は」
松尾「大丈夫じゃないってこともふくめて、120まで持たさなきゃいけないわけだから。枯れていくんだと思うのね。精神的にそれより前に枯れちゃったら死んじゃうんだけど、ちょうど120のときに枯れきるように……自分はどう終わるかって考えたときに、なんかこう……60歳だからようやく半分だと最近よく思ってるわけ。わかります?」
山登「いいね、長期的な展望だね」
松尾「長期的でしょう? でも、そういうことをイメージすることで……べつに長生きしたいわけじゃないんだけど、人生をまっとうしてみたいというか。要するに、120キロ歩かなきゃいけないんだったら、120キロ歩いて見せたい、と。80キロくらいで止まっちゃう人がいるんだけど、それは計画してない……120まで歩くつもりなかったでしょ、と」
山登「はぁ」
と、山登先生、なかばあきれ顔である。
私としても「120歳まで生きる」なんてファンタジーみたいなことを本気で信じてるわけではない。ぼんやりと考えたことがある、くらいのネタである。が、このときはなぜか、そのファンタジーを医師に話して正当性を確保したいくらいの勢いになってしまったのかもしれない。
松尾「だから、子どものこころなんていうことを山登さんと話しているのも、60になったら折り返しだから、もう一回、前のことから学び直そうと思っているわけでね。子どものモノの見かたとかを忘れているから、それを自分のなかに身につけることで、つぎの60年を見据えておきたいっていうか。
遊びは探索であるなんていうのは、ものすごく腑に落ちて……ああ、そうだったんだって……そうすると、これから大事なのことは、もう一回探索して、それが遊びだというんだったら、あれこれ探索することでつぎのおもしろいことが見えてくるわけじゃない?」
山登「うん」
松尾「っていう感じ……」
山登「それは非常に有意義だったね。最初にそのテーマを話したのは」
松尾「そうそう、有意義。そういう意味では、この病気と死っていうテーマに関しても、おとなの感覚がこびりついちゃってるんだけど、もう一回、それを洗い流して……洗い流すというのか、再度、確認してみたいと」
山登「ふんふん」
松尾「……という気はするね」
病気と死、そして衰え
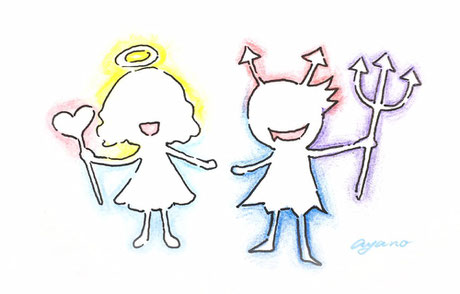
山登「おれのおふくろは、早々に70の手前でボケちゃって、10年後には寝たきりになって、さらに10年、寝たまんまんで、それで老衰で死んじゃったわけだよね。最後の10年はメシも食わなきゃ、話もできないという状態で、ただ寝てるだけ、お世話されるだけ。ああいうのを見てるとさ、120まで脳のほうが持ってくれればいいけど、脳のほうが先にダメになるっていうことも考えておいたほうがいいよね」
松尾「なるほど」
山登さんの的確な指摘に、ちょいとたじろぐ私である。いくら120歳まで歩きたいって言っても、体力より先に脳がダメになるいう問題はある。確かに。
山登「そうすると、どんな生きかたをするか。自分で死ぬつもりはないわけだから、どこでどんなふうに衰えて死んでいくのかっていうのは、心構えは必要だと思うけど、思うままにはならないね」
松尾「お母さんの最後の10年というのは、目は覚めないんですか。寝たきりっていうことは、ずっと眠ってるの?」
山登「ずっと横になっていて、起きてるんだか寝てるんだかわからない状態。親父が結局、ぎりぎりまで面倒みてて。うちの親父は小児科医だったから、胃にチューブ入れたり痰を吸引したり、なんでもできちゃうわけだよね。だから、たったひとりの患者を、毎日ヘルパーさんたちを看護婦がわりにして世話をしているという……最後は自分がくたびれちゃって、看取りをする病院を見つけて、おふくろを入れて、自分もそこに入院したのさ。親父は最後まで頭ははっきりしてたから、死の不安と恐怖と闘いながら死んでいったっていう感じだよ」
松尾「どっちが先だったんですか」
山登「親父のほうが先……おふくろはその2年半くらいあと」
松尾「お父さんとしては、お母さんの面倒をみることが生きがいになっちゃってたという……」
山登「そうそう、だから、ほんとに死ねないと思ったんじゃないの」
松尾「そういうことですよね」
山登「うん」
松尾「いよいよになって病院に行っちゃうと、自分の手を離れざるを得ないところで、生きる気力みたいなものもなくなっちゃったのかな」
山登「生きる気力……そうだよね、病院に入って自分がお世話される側になってさ。無趣味な人だったからなにをしていいのかわからなくなって、それでボケるかと思ったらボケなかった。そのへんは、自分の計算外だったんだね。もうちょっと豊かな老後が残っているかと思ったら……という感じだけど」
〇
うーむ。言いだしたとたんに「120歳まで生きるぞ宣言」があやしくなっていく感じである。「豊かな老後が残っていると思ったら……」という言葉は、ほんとに、せつない。けど、その指摘は正しい。120まで歩き続ける気でいたら、とてもさびしい一本道で、あたりの風景も荒涼として……なんてことは想像したくない。というか、想像する必要はないのかもしれない。そんな道をひとりで歩いていけるほど、人間はタフにはできていない。と、そこまで考えると「ボケる」という手もあるのか、と気づいた。荒涼とした一本道がお花畑に見えていれば、ルンルンと歩いていけるかもしれない。が、まわりがそれを許すとも思えないし、なにより、歩いている本人が幸福とも思えない。
子どもと話すべき、正解のないテーマ

さて、話を戻して。子どものこころを中心に「病気と死」について。
山登「子どもが考えるのは自由だし、考えて悪いことじゃない。それは、教育のチャンスだと思うんだよね、そういうことを話し合うのは」
松尾「チャンスね」
山登「そんなこと考えるんじゃありません、とかさ、そういう対応はダメだと思う」
松尾「だから、子どもと、そういうことが話せる機会があるなら、正解はないんだけど、パパはこういうふうに思うんだよね、とか。ペットが死んじゃった、どうしたらいいのってときに、親の考えを述べる。パパも子どものときに同じ体験をしたとか、ということしかない。なにも正解はないわけだから……」
山登「だいたい天国に行ったとかお星さまになったっていうオーソドックスな答えかたもあるじゃない」
松尾「たとえば、アメリカだったら毎週、教会に行く」
山登「教会にね、そうだね」
松尾「そういうなかで、神父さんの話を聞こうとかということで、そのあたりは教会に託すのかな、死に関しては」
山登「日本は無宗教みたいに言われてて……神さまの元に召されましたっていうふうには、みんな、思ってない」
松尾「どっちかというと、仏教系でしょう、発想は」
山登「だけど、極楽の蓮の池の、みたいなのは、子どもはイメージしないかもしれないね」
松尾「ウソついたら閻魔さまが、とか」
山登「いま、そんなこと言う親、いるのかな」
松尾「いないか」
山登「やっぱり教会があって信仰があってっていうのは、死の恐怖から逃れるための手立てだよね。そういうかたちで、日本には信仰が根づいてはいない」
松尾「昔はもうちょっと、お寺が近くにあって……寅さんだって住職が出てくる、御前様」
山登「肝試しとか、墓地でやって」
松尾「そうそう、墓地が身近にはあった」
山登「そういうものが遠くにいっちゃったんだろうね、現代人の生活は」
松尾「それはあまりいいことじゃないかもしれない」
山登「そうだね」
松尾「いまはお墓なんかなくて、エレベータみたいなことになっちゃってるわけでしょ?」
山登「お骨のマンションみたいな」
松尾「東日本大震災なんかで、3月11日になると追悼イベントがあったりっていうところで、受け継がれていくのかな。たぶん、関西の小学生なんかも、やってると思うんだよね、毎年。そういう意味じゃあ、東京っていうのは、よくない感じがするね」
山登「そうだね。災害に遭わないと考えないってことだよね」
松尾「それはよくないですよね」
山登「そういうところのリアリティっていうのが、災害でもない限り、みんなの意識から遠くに行っちゃってるっていうのは、よろしくはない」
松尾「お墓参りすら、東京にいるとなかなかできなくて……コロナで地元に帰れないから、お墓参りすることもなくなっちゃったり……」
山登「おれは両方とも両親死んじゃってるからさ、お墓参りは欠かさず行ってるし、お寺ともつきあわなきゃいけなくなっちゃって、大変っていうか、それまで人まかせだったのが……」
松尾「お墓って、どこかのお寺にあるわけでしょ?」
山登「うちは早稲田にある」
松尾「そうすると、自分はそこに入るけど……奥さんは?」
山登「おれは入るつもりはない。女房もない……海に散骨でもしようかと思ってる。うちは子どももいないしさ、おれが最後なので、墓をどうするかっていう判断はおれにかかってるわけ、山登家最後の人間だから」
松尾「永代供養料を払っておけば、面倒みてくれるでしょ?」
山登「おまかせして、自分は海に撒いてもらう、かな」
松尾「海に撒いてもらうのって、ぼくもよくわかる。森でもいいし……その感じでやってもらったほうが、いいなぁ。うちは子どもたちがいるから、お墓参りっていうより、海を見ながらメシでも食ってもらって、命日だねっていうほうが、いい。海に撒いてもらうっていうのは現代的な死生観だけど、すごく、共感できる。もう、お墓が、死を象徴しなくなってるんだよね」
山登「そうねぇ。イエも共同体も解体してるわけだし。なんか、お墓って、せまいところに閉じこめられるような感じがするんだよね」
松尾「確かに」
松尾「なんだかんだ、終わりのない話だね、病気と死って……」
山登「だから、子どものころ、ふと、死について考えたっていうのがスタートにあって、いまのおれたちの話がある」
松尾「考えるもんでしょ、だいたい子どもは、親が死んだら怖いなって」
山登「意外にちっちゃいころから、子どもはそういうことを考えてるんだ」
松尾「ちっちゃいころから考えるのに、そういう考えを深める材料が、ほぼないんだね」
山登「昔より少なくなって、体験としても薄れて……」
松尾「そこはひとつの課題だなぁ。いつもこうやって話をすると、最終的には日本社会の課題を提案してるね。学校教育の課題とか……」
山登「だって、ほんとに課題は多いよ。なんとなく先延ばしにしてるけど、みんな、どっかで考えたほうがいい……って言いながら、また先延ばしにしてるわけですよ」
〇
終わりのないテーマだし、あまりに抽象的で、結局はこの年齢になってもずっと考えている、ということだ。けれども、もし、子どもと「病気と死」について話す機会があるなら、ぜったいに話しておくべきだと思う。子どもたちの疑問に答えつつ、自分のなかに発見があるかもしれないし、逆に、そのことで、子どもたちにも発見があるかもしれない。考えても仕方ないことは話さないとか、答えがない話をしてもしょうがない、というのは、わりと現代では当たり前のように言われているけど、違う。
答えがないことにこそ、生きる意味とか価値が隠されていて、それを掘り起こすことがまさに「生きることそのもの」かもしれない。と、今回のテーマで山登さんと話すうちに、そんなことを考えたのである。

