子どものこころを
まんなかに
3. 食べる
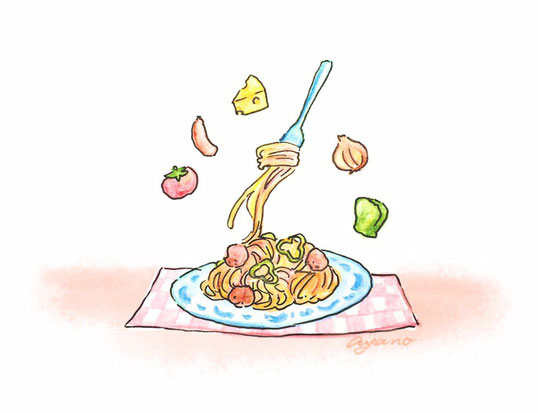
食べたいものを、食べたいように
「食べる」。生きている限り食べないわけにはいかないが、単純に栄養摂取というだけであるはずはない。おいしい食事、楽しい食事……などなど、いろいろと「こころ」に及ぼす影響もありそうだ。「子どものこころをまんなかに」して「食べる」とはどういうことなのか、『明治大学 子どものこころクリニック』院長で精神科医の山登敬之さんと対談しつつ考えていく。
〇
松尾「今日のテーマは『食べる』なんだけど……食べて栄養をつける……でも、子どもとしては、食べることによって自分のからだが成長していく自覚はないでしょ」
山登「そうね。おとなから栄養を取れと言われるとか、食べかたを躾けられるとかはあるだろうけど……でも、牛乳飲まないと背が伸びないと言われると、飲んで大きくなろうって思うよね。たくさん食べて大きくなるっていう実感はないかもしれないけど、意識はしてるんじゃないかな」
松尾「赤ん坊が食べるときって、散らかして、こぼしてってことをやりながら、好きなものを手に取って口に入れる。それはダメってスプーンの使いかたとか習っていく。養育手というか親は、学びじゃないけど、学習をさせるわけですよね」
山登「食べることを学習する?」
松尾「いや、食べかた……」
山登「食べかたね。マナーとか」
松尾「マナーっていうほどじゃなくて、こぼしちゃだめとか、そういうこと。赤ん坊が食べてるのを直してあげるとか、それもまた人間関係が成立しますよね。赤ん坊ひとりじゃ、ちゃんと食べられるようにならないわけだし」
山登「そうだね。食べるものにしても、食べかたにしても、当然、子どものころから学習していくわけだよね」
松尾「牛乳がきらい、ジュースが好き、この野菜はきらい、マヨネーズは好きっていうのも、食べて覚えていく……」
山登「偏食で親が苦労するっていうのはあるね。匂いとか舌触りとか、口のなかの感覚とかが敏感な子は、偏食がわりと強く出る。ピーマンとか緑の野菜がなかなか食べられない子どもは多いんだけど、それは、感覚が未発達というべきか敏感すぎるというべきか、そこらへんに原因がありそう」
松尾「野菜に関しては、ぼくらが子どものころよりも、いまの野菜って、わりと淡白になってるよね」
山登「食べやすい。まぁそれは、おれたちがおとなになったせいかもしれないけどね。はじめてのものは警戒してなかなか食べたがらない子どももいるけど、それを乗り越えつつ、幼稚園でも給食があり、学校給食もあり、まわりが食べるから勢いで食べられるようにもなる。だから、お母さんたちには、子どもは味覚にしろ口のなかの感覚にしろ充分に育っていないから、いまは食べられるものを食べてください、そのうち食べられるようになるからって言うこともあるね」
松尾「きらいなものも、大きくなると食べられるって言うもんね。酒の味を覚えると、苦い野菜もうまい、とかさ」
山登「無理に食べさせようとして、逆にそれがブレーキになるかもしれない」
松尾「家族で食べるようになり、幼稚園で友だちといっしょに食べるようになり……そうすると、食べかたみたいなものもだんだん学んでいくわけだよね」
山登「でも、食べかたっていうのは、手づかみからスプーン、フォークになり、箸が使えるようになり……遅かれ早かれ使えるようになってくる。そのあたりをうちで覚えてない子どもでも、幼稚園や小学校の給食で、指導を受けて食べられるようになるわけだよ。おとなになっても箸の持ちかたがおかしいとか言われるかもしれないけど、それはそんなに大問題ではないよね」
子どもがまだ幼いうちは、あまりむずかしいことは考えずに、食べたいものを、食べたいように食べるというのが健康的なのかもね、という気はする。とくに「子どものこころ」の側から言えば、食事がむずかしいものであるはずもない。できるだけ楽しく食べるのが、まずは大切ではないだろうか。
食卓の風景に正解はないけれど

松尾「家族の食卓の風景みたいなものは、時代とともにどんどん変わるじゃない? 家族ごとにも違うしね。お祖父ちゃんお祖母ちゃんがいて食べてる家族もあれば、母親しかいないうちもあるし……子どもにとっては選べないから、それが最高かどうかわからないけど、これが自分ちなんだってことだよね」
山登「当たり前のね」
松尾「味に関しても、おふくろの味問題っていうのがあって……おふくろの味なんて、もう言っちゃあいけないんじゃないかって言葉でしょう」
山登「家族の食事はお母さんがつくるもんだっていうのは、ダメだろうね」
松尾「ダメですよね。だからといって、お父さんがつくるっていうわけじゃなくて、惣菜を買ってくる」
山登「そうだね。おふくろの味じゃなくて、コンビニの味」
松尾「コンビニの味、スーパーの味。だからといって、問題があるわけではないよね」
山登「そうね。令和の時代の食文化っていうのが、どうなっていくのか……おれなんかは、完全に昭和のサザエさんみたいな感じだよね。卓袱台囲んで家族みんなで食べる。それがおれのベースにある。大学に入ったときに、サークルの後輩で、高校時代は親に反抗してたから、部屋でひとりで食べてたって女の子もいたね。べつの子は、うちのお母さんは料理をつくらなかったから、夕食はみんないっしょにひよこ食堂でって……ひよこ食堂って名前かどうかわからないよ、自分ちのとなりにあった食堂で食べてたって子もいた」
松尾「ハリウッド映画を観ていると、ほぼ、晩ごはんをつくるシーンは出てこないよね。朝ごはんはつくってる風景っていうのは、シリアルとか牛乳とか目玉焼きとかソーセージとかって登場するけど、晩ごはんって誰もつくってない。いつも、中華ヌードルとか、ピザ取ったりしてる。アメリカの食生活って、あれなんだろうなぁ、きっと」
山登「どうなんだろう」
松尾「家庭によるか……」
山登「お母さんがつくってる家もあるんじゃないの? けど、向こうの人は、夫婦で夜、遊びにいったりするからね」
松尾「だから、卓袱台囲んだ家族の風景っていうものは、実はあまり関係がないというか、子どもにはそれがすべてだから……うちは夜はいつもピザなんだなとか、そういうことで成立しちゃうわけだよね」
山登「ファミレスなんて、おれたちのガキのころはなかったけど、いまは全盛だよね。おれたちのころは外食ってちょっと贅沢というか、よそ行きの感じだったけど、いまはふつうに、きょうはファミレスでって感じになってる」
松尾「ファミレスに行くと家族がいて、ドリンクバーがあって、小さな子どもがぎりぎり届くか届かないかのボタンに手を伸ばして、半分までカルピスを入れて半分はメロンジュースとか……きっとよく来ていてスキルがあって……子どもはそれで楽しいと思うんだよね、好きな味が出てきて……。昔とは、家族の食卓のありようがまったく違っていて、ファミレスも、いまの子どもたちの原風景になっていくんだろうな。いい悪いじゃなくて」
山登「濃い色のついたジュースなんて、昔は、なかなか飲ませてもらえなかった」
松尾「いまはそれがふつうでしょ」
山登「そうかもね」
松尾「子どもに悪いものは食べさせてはいけないっていう、ファミリーレストラン側の前提もあるし。アレルギー表示もあって……」
山登「ファミリー向けにはそういう配慮をしないといけない」
松尾「ファミレスでハンバーグ食べたり、カレー食べたり……パパもいてママもいて兄弟もいて、わいわいと盛りあがっていく……それが、いまの食卓なんだよね」
山登「松尾くんのおうちはどうだった?」
松尾「これに関して……ずっと思い出してたんだけど、うちのおふくろはね、ほぼ料理をつくれなかったんじゃないかと思う」
山登「そうなの?」
松尾「そのことに気づいたのは、結婚したあとでね」
山登「そういうことは、あるね」
山登「山登さんもエッセイに書いてたけど、自分の実家と、妻の食生活を比較して……いまはカミさんのおふくろさんも同居しているので、自分の母親が手伝ってくれたりするしね。母親の旦那、つまり、お父さんは、ものすごく食事にうるさい人だったらしく……」
山登「ふうん」
松尾「あれをつくれ、これつくれって、おふくろさんは毎日泣きながらつくってたらしいんだよね」
山登「それはかわいそう」
松尾「そういう環境でおふくろさんは鍛えられてて、凝ったものだってなんだってつくれちゃう。ぼくとしては、はじめて食べるものがたくさん出てくるんですよ。そう言えば、うちのおふろくは、電子レンジが世のなかに登場しはじめたころに、毎日キャベツを半分に切って、チンして塩をかけて出してたなぁ、とかね。それは極端な思い出かもしれないけど、ほとんど料理をつくらなかったんじゃないかと」
山登「そのころはわかんないもんね」
松尾「そういうもんだと思ってて……うちの親父は黙って食う人だったのね。お父さんになにをつくってもおもしろないわ、なんにも言うてくれへんからって……うちのおふくろは、よく言ってた。ぼくもそういうものだと思ってるから、あんまりうまいのからいのしょっぱいのって言わない。もしかすると、うまいものを食べてないから、味覚音痴かもしれない。でも、どうやら、うちのカミさんにとっては、それがよかったみたい。自分の父親がうるさすぎて家庭が殺伐とした感じになってたから……。でも、この年になってようやく、あなたはなにも言ってくれないって怒られる。だから、最近は、おいしかったと言うようにしてる」
そうやって個人的なことを告白してるわけだが、そういう「家での食事」の記憶を持つ私は、「食べる」ということに関して、いい思い出も悪い思い出もないわけである。ひとりっ子ということもあり、家での食事は実に淡々としたものだった。笑い声をあげながらワイワイと食卓を囲んだ思い出っていうのが、とにかく、ない。
食事は、人間関係の基本ではある

松尾「ファミレスで、子育て中みたいな家族も見るんだけど、このお父さんは知的な仕事をしてるんだろうなとか、お母さんは頭よさそうだなっていう家族と、わりとジャンクフードばっかり食わしてるんだろうなっていう家族……まったく違うもんね」
山登「親はスマホ見てて、子どもはギャーギャー騒いでるとかね」
松尾「全員スマホを見ながら食べてる家族もあれば……会話がはずんでて、ああだこうだと楽しそうな家族もいて……となりに座ったおじさん目線で言うと、家族の食事風景によって、子どもの発達は違ったものになるだろうというのは、ある」
山登「ありますよ。家族の食卓っていうのは、子どもが育つ重要な場所だからね。前回の話じゃないけど、学びという意味では、マナーもそうだし、ちゃんと栄養のあるもの食えてるかどうか……焼きそばをおかずにチャーハンとか、そんなもんばっかり食わされてたりしたらさ(笑)。健康も文化も、基本はやっぱり家族の食卓じゃないかな。そんなことばっかり言ってると、古いって言われるかもしれないけど……」
松尾「実は食事って、いちばん会話が成立する場所なのかもね。これがおいしいとかおいしくないからはじまって、○○ちゃんはこういうのが好きだよね、いや、これも好きだよあれも好きだよとか、そういうふうに会話がはずんでいく。そんな家庭もあれば、ずっとスマホを見てるとか……かといって、親はスマホばっかり見てるんだけど、いっしょに食べてる兄弟は頭よさそうだったりする子もいたり……ピチャピチャ音を立ててるお父さんもいれば、きれいに食べる人もいて……そばで見てると、これはすごいことだなとは思うよね」
山登「うん……」
そういう意味では、私の子どものころの食卓は「さみしい」ものだったということになる。きっと、父親も母親もそれでよかったのだから、そういう雰囲気の食事になっていたのだろう。ファミレスに行ってよその家族を眺めていると、ほんとに、食事風景はそれぞれで、きっと子どもが獲得する感覚も、実にさまざまなのだろうなぁと思う。でもきっと「これが正解」というものもない。
松尾「子どもの食べかた問題で悩んでいる母親が、クリニックに相談にやってくるってこともある?」
山登「それがメインでは来ないけど、いろいろと発達上の問題が出てくるときに、さっき言ったような偏食がひどいとか、小食……そもそも食べないとか。食事中に座ってないとか、そういう食事がらみの話題は出るよ。とくに、幼児から小学校にあがるくらいまでの子だと、そういう話は多い。やっぱり食っていうのは、育ちの重要なファクターなんだよね」
松尾「小食というのは、食べないわけ?」
山登「食べない。食に関心がない。落ち着きがなくて食事が終わるまで座ってないとかね。座らせて無理に食べさせようとするとまた子どもが癇癪を起こしたりするから、じゃあ、食べられるときに食べさすかみたいなさ。そうすると、一日三食とか、なかなか習慣がつかないんだけどね。それにしたって、成長すればちゃんと、だいたい決まった時間に食べるようになるんだから」
松尾「食事中になにかを矯正されてるっていうのは、楽しくないもんね」
山登「楽しくないね」
松尾「楽しくないものには、参加したくないし……」
山登「うん。夫婦の仲が悪くて、食事中、ぜんぜん会話のないうちだってあるだろうし……。やっぱり、仲が悪くなると、いっしょにメシ食いたくないよね」
松尾「はいはい」
山登「昔の職場で女の上司とさ、昼飯は病院で店屋物取ったり、外に行って食べたりしたんだけど、その人との関係がダメになったときは、真っ先に、いっしょに食わなくなったもんね(笑)。やっぱり、いい関係のなかで食うメシじゃないとうまくないんだよ」
松尾「そういう意味では……これは教育とも子どもとも関係ないけど、いっしょに食事をしたくない人って、基本、人間関係的にダメってことだよね」
山登「だから、大勢で食事をするっていう習慣も……最近、接待とか仕事ならべつだろうけど、つきあいのメシっていうのは、避けたいやつは避けるし、それも許されるようになってきた。個人の裁量のうちってことで、意思にまかされるようになって、昔みたいにメシ行くぞー! っていうノリは、ないわけだよね。そういう若者だって、いつもひとりでメシ食ってるわけじゃなくて、仲のいい友だちとか同僚とか、恋人とは食ってるわけだよ」
松尾「そこは、素直に、楽しい食事はしたいけど、上司とおもしろくない食事なんて、時間がもったいないってことじゃないの」
山登「やっぱりさ、デートに誘うときも、最初にいっしょにメシを食おうって誘うわけじゃない?」
松尾「そうだね」
山登「仲良しの印なわけですよ。それはほんとに、子どものころからの積み上げがあってこそじゃない?」
松尾「デートのときに食事に行って、いきなり醒める……食べかたを見てとか、選ぶものとか、頼みかたを見て、いきなり醒めちゃうっていうことがあるから、まぁプロセスとしては大事なテストになるしね」
山登「だから、まずメシ食いに行かないと」
松尾「そういうことかも」

「食べる」こそが人生
松尾「子どもにとって『食べる』っていうのは、学習とか学ぶ、人間関係を学ぶっていうか、そこで成立する人間関係の機微みたいなものもふくめて大事な時間ではあるけど、こうだからいいとか、こうだからダメだっていうのは、なさそうですね」
山登「松尾家の話じゃないけどさ、結婚してみてとか、社会に出てみてとか、そこから広がっていくわけだよね。だから、子どものころにこうでなきゃいけないっていうのはないかもしれない。そこではじめて出会って、そこで学んでいくこともあるから、ひよこ食堂で食ってていい気もする」
松尾「一杯のかけそばって話があって、あれはあれでなんで泣けちゃうかというと、一杯のかけそばを母とふたりの子どもが3人で食べてる……こっちから見るとつらそうだな、もっと食べればいいのにってことなんだけど、その親子が分けあってる感じとかが、実に、ふつうに成立してるから聞いてるほうは泣けてくるっていう……食事は生物として基本的なことだから、愛情とか、すべてそこに集約して現れちゃうのかもしれない」
山登「一杯のかけそばの反対で、ゴッドファーザーみたいな映画を観ると、大家族で大勢の人が、すごい豪勢な食卓で長い時間をかけてメシ食ってるじゃない。イタリア、フランスなんかは、昼休みとかメシ食う時間も長いわけだよね……階級によるのかもしれないけど」
松尾「よく言うよね、イタリア人の若い男は、みんなママンのパスタがいちばんって言う、みたいな」
山登「大勢で長い時間をかけてメシ食って、おとなはワイン飲んでみたいなね。でも、最近は、おれたちの頭にあるような、映画で観たような食文化っていうのは、向こうの国でも崩れつつあるかもしれないね」
松尾「ベースにあるのはぼくたちの知ってるああいうもので、だんだん変わってはいるけど、基本的なところは変わらないのかも知れないし……まったく新しい食文化……ファミレスみたいなのが出てきているのかもしれないし……」
それぞれの家庭で違う、国によっても違う……ほんとうに「正解」はないのだけれど、確実に、どこでもいつも「食べる」は存在する。だからこそ、どんな雰囲気でどんな会話があるのか、そういう積み重ねが、子どものこころにじわじわとなにかを蓄積していくってことかもしれない。
松尾「あと、あれはどうですか、お菓子……お菓子ばっかり食べてふつうの食事ができなくなるってことも、あるでしょ?」
山登「確かにそういう相談もあるね」
松尾「スナック菓子もジャンクフードっぼくなってくると、麻薬のような魅力がある。子どもにとっては。あれはちょっと問題だよね」
山登「親がきっちり、我慢することも教えないといけないよね」
松尾「麻薬に手を出してはいけないっていう教育だね」
山登「昔は、駄菓子屋さんにお小遣い持って子ども自身で買いにいって、そこのおばちゃんとコミュニケーションがあったけど……いまはコンビニでレジで、子どももおとなと同じように対応されて手に入る……おれなんか、駄菓子屋なんて行かせてもらえなかったけどね」
松尾「駄菓子屋……ぼくは行ってましたけど、ちょっぴり悪の匂いが……不衛生な感じもするし、ビンの中にスルメが入っていたり、食っていいかどうか、なんの肉かよくわからないとか……みょうにおいしいものとか、すみっこにへんなおもちゃがあったり……」
山登「子どもにとっての誘惑がある」
松尾「必ずそこにいるのはガラの悪い先輩、みたいな」
山登「ああ」
松尾「そういうのがたむろしてるから、行っちゃいけない感じはあったけど、自分が学年上になって行けるようになると、ビビったような後輩がいて、まだガキだね、みたいな」
山登「社交場だったんだね」
松尾「そう、たぶん、駄菓子屋って子どもの社交場……おばちゃんとかが管理してて、あんたいま盗っただろってバレてたり」
山登「いまは、駄菓子屋に代わる場所ってあるのかな」
松尾「どうかな。コンビニはコンビニだけど……きっと場所を移して、そういうのはあるのかもしれない……。でも、とにかく、ジャンクフードでおなかいっぱいになっちゃってメシが食えなくなっちゃう、親が気づくか気づかないって家庭環境によるし、みたいな」
山登「うん」
松尾「一筋縄ではいかない。それぞれの家庭があるから」
山登「栄養学的にはまずいわけだよね、それは。虫歯にもなるし。そこは、親がきちっと躾けられるかどうか。われわれがガキのころよりは、そういう誘惑も多いし、親の目は届かないし、みたいな感じだろうし。子どもにとってなのか、親にとってなのかわかんないけど、むずかしい時代だよね。実態がおれにもよくわからない」
料理がヘタッピな母親ではあったが、少しずつスーパーに並びはじめたレトルト食品をいっしょに買いに行っては「これはおいしそう」だの「これはいまいち」だの言っていた。きっといまなら、大量に並んだ冷凍食品コーナーで会話がはずんでいたかもしれない。食事はあまりに日常だからこそ、そこでの気持ちの交流がものすごく大切なのだ。少なくとも、食事中のスマホはやめたほうがいいと思う。
学校よりも家庭の役割が大きい
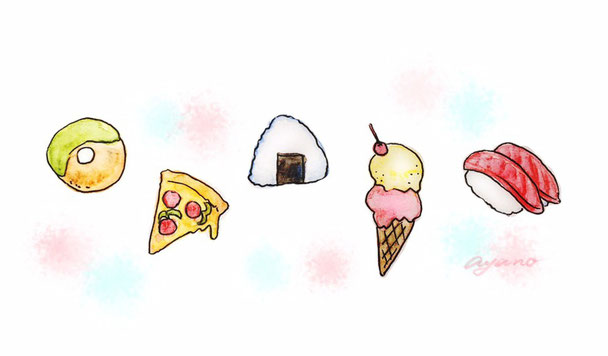
松尾「子どもにとって食べることは、間違いなく、喜びではある」
山登「そうでしょう。食べないと生きていけないわけだから。文化以外のところでも、食べてお腹がいっぱいになって満足するっていうのは、生きもののベースとしてあるわけじゃない? ここにたまたまユニセフから届いた『食べることは生きること』っていう小冊子があって……これを見たら、世界には5歳になる前に死んじゃう子どもが毎年520万人くらいいるんだって。しかもその半分は、いわゆる栄養失調。最近は、発育阻害っていうらしいけど……慢性の栄養不良のことだね。栄養が足りなくて死んじゃう子どもが、250万以上いるっていうわけだよ。それで、1000日プロジェクトというのをやって成功したっていうんだけど、お母さんのお腹にいるときからふくめて、要するに受胎してから1000日……2歳の誕生日までの栄養をしっかり摂らせると、その先が違うっていうわけね。しかも、母乳で育てましょう、と。母乳が最高の食事だと。免疫力があがって乳幼児死亡率が落ちるんだろうな、ちゃんと栄養を与えると……」
松尾「いきなり、そこかよって話だね。いままで話していた家族の団欒だなんだって、全部ひっくり返して、260万人の子どもがって……」
山登「生きものだから、食べないとはじまらない」
松尾「食べたいんだけど、なにも与えてもらえない……精神的にというか、子どものこころとしては、つらいよね……食べたい、なにもない、食べたいなにもない……胸に迫る、つらいなぁ」
山登「ネグレクトとか……この前も、福岡で洗脳された母親が、子どもに食わせなくて、5歳の男の子が死んじゃったという……ああいう話を聞くと、想像するだけでね」
松尾「あれを想像すると、ただただ、胸がつまるしかなくて……母親がそういう態度に出てるわけでしょ? 自分に与えてくれない……」
山登「お腹が減ってるのに、食べるものを与えられない……」
松尾「ん? 話が広がりすぎて、落としどころが見えなくなった気もするんだけど……」
山登「この前の学ぶと結びつけて考えたらいいんじゃない? たんに栄養を摂ってからだを育てるっていう生物学的な側面だけではなく、人間関係を学ぶ、文化を学ぶ。それが、同じくらい重要なこととしてあるという……」
松尾「その環境は、実は、子どもは選択できないから、意外に、こちら側、親の側がきちんとそういうものだと思って、食事の時間とか、どうやって食べるとか、どういうものを食べるとか、少しずつだけど、すべてが大切ではないかというのが結論かな」
山登「いろんな家庭の事情があるから、おれたちの頭のなかにある家族の食卓ってところに話を戻しちゃまずいとも思う。子ども食堂とかやってる人たちもいるけど、そういうふうに社会が支援していく、そこからなんだよ。食事から、その様式から、新しいことを考えていかないといけない。なにごとにも基本と発展があるわけだから。とは言うものの、子どもが成人して家を離れていくまでは、食のテーマというのはすごく重要だよね。自分で好きなものを食べられるようになるまでは、親と子どもは、影響を互いに与えあっている」
松尾「前回の『学び』ってテーマよりも、家庭の役割が大きいかもしれないって気がしてきた」
山登「そうだよね」
松尾「親はいっしょに勉強を教えたりってできないけど、食べるはもう、ファミリレスに連れていこうがどこで食べようが、いっしょに食べる人がいちばん長く時間を過ごす……」
山登「学びは学校があるから親はそっちに任せられる。でも、メシを食うとなると、まず家からだもんね、外に連れていくにしても……それは親がきちんとやってくれって話だよ」
食べる……内容はともかく、親の愛情とか気持ちが、子どもに確実にじわじわと浸透する時間なのである。だからこそ、おとなは、子どもと食べる時間を大切なものとして考えておいたほうがいい、というのが、今回の結論だろうか。世界には毎年250万人の子どもたちが発育阻害で命を落としている……その現実を胸に刻みながら、自分の子どもを見つめると、思わず笑顔を浮かべて話しかけたくなる。
「おいしいね」
そのひとことから、ってことかな。

